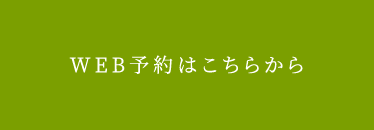鮨を知る
 UOTAKE SUSHI
UOTAKE SUSHI
すしの材料知識

2021年10月4日
酒粕酢
1804年に熟成させた酒粕だけを原料にして酒粕酢が出来た。 1810年頃、江戸前ずしは、この酢と出会ってはじめて隆盛の一途をたどる。 それまでは酢といえば米酢だけだった。昔の酢は杉の樽に入っていてコクあった。 米酢のように酪酸臭のない酢よりも江戸時代の強い香りのする酒粕酢の方が旨い。
酒粕酢での合わせ酢は熱すると匂いが確かに強い香りがする。 シャリに少しぐら色がついたリバイバル粕酢使用の「すし」を当店でご賞味下さい。
山葵
良いワサビ
①緑色していてさわやかな香りと甘さがある
選び方
①キズや黒ずみがないもの
②頭部も先端も細くなく、円柱形に近いもの
③緑色が濃くみずみずしいもの
おろし方
①流水で洗い皮をむかない
②頭部すなわち茎の方がみずみずしいく新鮮なので
③「の」の字を書くように
保存方法
①1週間以上保存する時は表面の水分をふき取って密閉し(ラップ)冷蔵庫へ
江戸前握りすしとつけしょう油
「江戸前の握りずしは、しょう油をつけてたべるものか、それとも、つけずに食べるものか」
いまは、握りずしはしょう油をつけて食べるのとされているが、これは食べ方としても、おかしな話である なぜならいうまでもなく江戸前鮨の特徴はいろいろ違ったタネ(ネタとはすし屋は言わない)の持ち味を生かして、それが飯(すし用語ではシャリ)と調和(なじむ)するところにあるのだから、それを、つけじょう油につけることによって日本食の基本である十色の味を一色に近づけて食べるのはというのは感心できない。すし屋にしても、それではなんだか馬鹿にされているようなものである。
まして、タネだけズルリと剥がして、それにしょう油をベットリつけたタネをまた、もとの飯の上にかぶせて食べられたのでは、見ているこちらのほうもガッカリさせられてしまう。
もっとも、そのくらいにして食べなければ旨くない握りも、昨今ではままあるのだから話は面倒である。
だが、昔(明治末期まで)は、つけじょう油なしで食べられる握りが普通だった。・・・・・・・・。
結局、つけじょう油とは前処理や煮きり(生醤油を自家製の味に)を使わない純生物をタネとした握りずしの出現によって必要となったに違いない。・・・・・。
そして、純生物のタネを使うということは、江戸前伝統の技術からいえば一種の逃げ仕事であった。
煮切り
搾りたての生醤油は、本来の味と香りを大切にするので醤油自体に一切味付けをしないの で、すぐにカビが発生します。普通の醤油はしぼった後に加熱殺菌をして、保存性はよくなりますが、反面醤油本来の香りの良さがなくなります。日本酒『生酒』の吟醸や大吟醸が冷蔵することで腐敗を防ぎ、流通されています。
これをヒントに搾りたての生醤油も、冷蔵することにより本来の味と香りを大切にした生醤油が流通販売されております。江戸前鮨屋では生醤油の強い香りが、淡白なすしの味がこわされてしまいますので、そこで江戸時代から「煮キリ」といいまして生醤油を、各店独自の工夫で味を作り上げております。こだわり
浅草の海苔
江戸の中期までは江戸の味覚といえば上方(大阪)から「下りもの」で江戸中~後期にかけて江戸の 独自のものが、江戸で生まれた。当時は海に近かった浅草を物資の流通拠点としたことから浅草と海苔の関係が生まれる。 上方(大阪)に流通した最初の商品が海苔である。しかし、埋め立てが進むにつれて浅草では海苔の採集ができなくなった。 寛延2年(260年前)海苔の発生に不可欠な貝類が江戸川の氾濫で埋まってしまい漁具や浮遊物に付着する海苔を採取する漁法はできなくなる。それ以降の享保2年(1717)生産地は品川に移る。このころから「ひび立て」による養殖が始まり生産量が増大した。 享保2年(1717)ころ品川浦で始まった海苔養殖は天明ころ盛んになり、江戸の名所になりました 時代末期になると品川の養殖は衰退し中心は大森に移る。生産者の大森の生産者は日本橋ののり商と取引を拡大したので、浅草ののり商人は凋落し、浅草は「あさくさのり」の名前だけを残して脱落する。 需要が庶民に浸透していく手助けは江戸市中を天秤棒で担いで売り歩く「振り売り」であった。 地方に売りに出る「旅師」も、長野県諏訪の人達であった。江戸式製法が始めて箱根を越えたのは文政2年(190年前)のことであった。(握りずしが考案された時期に重なる) それほどに江戸湾ののりは閉鎖的な生産、流通のもとで成長してきた。
江戸と上方の昔の合わせ酢
食酢の歴史
平安時代延期年間(927年)に延期式に米酢の作り方が記載されている 桃山時代までは和泉酢大阪 の独壇場でした。 江戸時代前期には相模の中原、駿河の善徳寺(富士市)、尾張の半田などに伝えられ、名産地が誕生しました。 年代までは米酢が一般てきであった。上方の押しずしのすし飯には、日本酒から造った米酢が使用され、砂糖も使用されたもようである。 一方、江戸時代も後期の文化・文政年間になると、「握りずし」が考案された。 文化元年(1804)「高価だった米酢を粕酢にすることができたら・・・」ミツカン酢は酒粕を利用した粕酢造りが始められました。 塩の歴史「入浜式塩田」500年位前(室町時代末期)から昭和年頃まで続けられ、この自然の力を利用した大変合理的な方法は、干潮と満潮の差が大きい瀬戸内海沿岸で開発・発展しました。
砂糖の歴史
寛政2年(1790讃岐(香川県)で白砂糖が製造され、年後には大阪市場に廻送できるほど量産化された。 砂糖には、すし飯に粘りや艶を与えるという利点もあるし、これを使うことで保存性も高くなる。さらに、砂糖の持つ保水力で、酢をご飯粒につなぎ止めておくという効果もある
江戸の昔の合わせ酢
シャリ1升(1800cc)
酢1合(180cc)
塩1合(180cc)
すし飯は、現在のように塩と砂糖を加えた酢を炊きたての飯に混ぜるのではなく、塩は炊き水に加え、砂糖は用いず、酢はすし箱に詰めてから適量を振りかけていました。塩が現在の分量の約3倍と多いのは、塩の精製度が低いためで飯は粕酢と塩だけで味付けがなされ、上方の押しずしとは異なり砂糖を使用しなかった。
関西の昔ながらの合わせ酢
粕酢(赤酢と称する)はシャリが黒くなりますので関西では米酢を使用(江戸の握りはタネで見えにくいので粕酢を使用)味付けには塩・米酢・砂糖昔は味醂を飯に入れて炊いたので焦げるので合わせ酢に砂糖を使用。 砂糖は冷めても美味しく食べられるように砂糖を使う。 コンブは米1升につき 20匁の割合。 宵から水に漬けて水だしをとり水と合わせます。シャリの温度が下がるにつれて砂糖、塩、酢がバラバラになるのを昆布が防ぐことができる。 現在でも適用されている合わせ酢である
お茶
寿司の材料にはのり、すし米、わさび、しょうが、お茶がある すし屋のお茶汲みは三年修行しなくてはいけないと昔から言われてきている。 親方が「あがりだよ」と、云いつけるときは、お客さまの、すしたべるのが終わりだよ」 と云う合言葉である。「お客さま、お帰りだよ」「もう、たべるのは済んだ」になる。 お変わりの二杯目のお茶を持参いたせの意味にもなる。 知識 すしの肴のあぶらというものは舌先に必ず残る。そこで次の味覚を得るのに、濃くて熱い茶をすこしづつ飲んで消そうというのである。 舌先にあぶら気が残る、それを消す茶も熱いのが必要のために湯のみ茶碗は大きくて厚く、熱いのが手に持っても外に伝わってこないので、二重の用を足している。 お茶は熱くてなくてはいけない。店によって気取って薄手の茶碗を使って熱くて手がつけられない。これはすし屋としては失格である。 鼻で香りをかいただけで静岡の茶所の老主人はこの茶の木のあった近くに梅の木がある、桜の木がある、と臭覚の発達ですぐ判ると云っている。茶は敏感に移り香を吸収するものだそうだ。
むかし江戸城にお茶汲坊主という、大名などにお茶を接待する役の男は、みんな頭をそって坊主頭であった。茶男だけが坊主頭かと云うと、茶というものは脂気を嫌う。 茶汲男がまげ(びんづけ油)を結っているとちょいと、指が頭の毛にふれる、それを知らぬまま茶器をいじる、そうすると汲んだ茶に脂気がうつるということになる。 だからお茶汲男は坊主頭にしているのである。 すし屋のお茶は、色と香と味の三つが揃わねばならない。お茶自身から出るなんとも云えぬ甘味が、すしの味をを傷をつけるものである。 それほど茶というものは、味に関連が深い。そこですし屋ではクセのないものを使うのが一番安全いうことから静岡地方のお茶で、粉茶を多く使う。 粉茶は葉茶より早く、茶自身の香と渋みを出すからである。 すし屋のお茶汲みは三年修行しなくてはいけないと云うほどに、むずかしいもである。
ショウガ
すし屋の符諜では「ガリ」という。 手酢・ワサビ・ハラン等と並んで抗菌力のあるすしには無くてはならない必需品で、 オオバ、ホージソ、キューリと共に妻ものと称しております。 これらの品を取り扱う専門の妻屋さんがありまして、こちらからショウガを持ってきて頂いております。 このショウガに味をつけるのは自分でするのが望ましい。風味、歯ざわり、香り、全てにわたって国産で無いものとは違います。
ガリの製法
以前はショウガの外側の皮をむいて薄く下したものに、 摂氏60度から70度ぐらい熱いと感じる程度の湯をかけるのを「湯ぶり」という。 そしてすぐに冷水にくぐらせて、アクを抜く。こうすると臭い色は消えて色を美しくして舌ざわりを和らげる 特色がある。 湯ぶりすませてから、酢2、砂糖1 塩少々の甘酢に漬ける。
海苔巻
上方と江戸との違い
上方(関西)は「巻きずし」という。江戸(東京)は「海苔巻き」という。 江戸で細巻きの考案されてから太い海苔巻きを「おお巻き」と呼んだ
上方の海苔は焼かない。江戸は焼いた海苔。 江戸の海苔はツヤがあり、パリッとした歯ざわりがある。巻く時はすばやく 「巻簀(すのこ&簾=すだれ)」で巻く。 上方の海苔は生(焼かない)だから破れる心配はないのでぬれ布巾に包んで巻く。
江戸風の大巻き
江戸風の大巻きは飾り巻きずしに見られるように派手に巻く。 これらの海苔巻きは明治初期に考案された。当時、江戸料理は見た目の楽しさを追求するあまり、食べてみての旨さを忘れかけて 命取りになったともいわれている。
細巻きすし
昨今は細巻きすしを切らずに1本のまま食べる人が多くなっている。 食べるには理屈は抜きにして要は旨ければ良いのであるが、 昔から細巻きすしの包丁の約束になっている事は承知しておくことも必要である。
細巻き かんぴょう巻は戦前までは三つ切りが普通であった。これを江戸ッ子は遊び言葉でチャンチキ(馬鹿囃しの太鼓の撥が 本だから)と呼んだ。戦後になって一切れ余分になるので四つ切りにするのが常識となった。>何故か判らないがすし屋の先駆者達はオボロ巻は四つ切りの方が旨いと言う 但し、鉄火巻、玉子巻、穴子巻は六つ切りである。 カッパ巻、お新香巻、奈良漬巻は合間に食べるお茶うけ代わり (お菓子がお茶を引き立てるとう意味に転じ、「お茶請け」という語が使われるようになった・・・) といことで巻きずしは1本を八つに切る(八つにおろす)と約束事になっていた。
シャリとうちわ
江戸前の鮨を営むすし屋では昔ながらにごはんに強い味付けがしてあると、すしダネの味を引き出せないので、 酢と少量の塩だけで自然の甘さを生かすためにも、酢合わせ(酢の調理法)には砂糖を使用しない。
この酢合わせの調合は門外不出で昔から奉公明けに教えて頂く技術なのです。
しかしながら関西のすしは冷めても美味しく召し上がれるように砂糖を入れる。又、甘いがうまいという味覚になっていますので、現在江戸前の80%以上のすし店では砂糖を入れる酢 合わせになっていると思います。 ご飯は釜の中で炊き上がってから数十分以上蒸らされた状態の後、ご飯を切ります。これをシャリきりと いいます。
シャリきりをしている時に扇風機やうちわで入れるのはごはんが冷たくなりほぐれにくくなりますのでこ れはいけません。 シャリきりが終わった時点で自然の風やうちわ風を入れて「てり」出す程度が良いでしょう。
シャリを握る極意
名人といわれる某鮨職人の握りは「やわらかく、空気を握りようなのだ。 タネにシャリをのせてから親指で軽く押し、くるりと丸める。 シャリ一粒と一粒のあいだに空気が入るため、やわらかく感じる。 それを食べると、歯切れのいいシャリと上等なタネがからみあい シャリガがホロリとくずれて、えもいわれぬ味をひきだすのだ。 魔法の握りとはこのことだ。