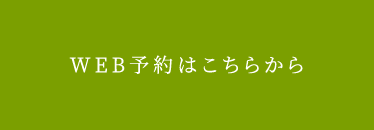鮨を知る
 UOTAKE SUSHI
UOTAKE SUSHI
こぼれ話

2021年10月7日
江戸のすし文化とこぼれ話
釣瓶ずしと歌舞伎
すし屋弥助がモデル
延享3年(1746)に完成した竹田出雲の『義経千本桜』には、源氏に破れた平維盛をかくまう役どころとして、このすし屋が登場する。
あらすじ 吉野山中をさまよっていた維盛は、釣瓶ずしを商うすし屋の弥助に遭遇する。弥助は、かって維盛の父重盛に恩義を受けていた人物で、自ら家に作男として維盛を招き入れ、家族にも内緒で、敵の目を欺くことにした。この時、弥助はその名を維盛に譲り、自名を弥左衛門と改名する。
維盛は、いつしか弥左衛門の娘お里と恋仲になり、祝言を上げる運びになるが、その前夜、維盛を案じて吉野を訪ね歩いていた妻子と再会する。すべてを悟ったお里は、父とともに維盛一家の逃亡を手助けする。しかし、お里の兄で名うての厄介ものである権太が維盛の正体を聞きつけ、維盛の身柄を源氏の追っ手に引き渡すと宣言。一足先に家を出た維盛たちの後を追い、やがて「維盛の首を取り、妻子は生け捕りにしてきた」と帰ってきた。 居合わせた源氏方の梶原景時、首の入ったすし桶と妻子を引き渡した権太は、褒美をもらうが、逆上した弥左衛門に斬りつけられてしまう。死に際権太が言うには、桶の中の首は、あらかじめ弥左衛門が準備しておいたもの、差し出した妻子は自分の妻子だという。はたして、維盛一家は元気な姿で現れる。権太は改心し、わが身の家族と引き替えに維盛を守ったのだった。
その後、首と妻子を連れて行った梶原も、すべてを承知の上で維盛一家を見逃したことも判明。維盛は一人出家するとて、吉野を後にする。
森の石松の食べたすしは?
森の石松の食べたすしは? 大坂で買ったすし 講談や浪曲で演じられる「石松30石船」は、「江戸っ子だってね」「神田の生まれよ」「食いねえ、食いねえ、すし食いねえ」の名セリフでよく知られている。芝居などではこのすしは江戸前風の握りずしとして仕立てられることが多いが、この場面は金毘羅代参を終えた帰り道の、大坂から京都伏見に向かう淀川の船上でのできごとで、次郎長一家を誉められた石松が乗り合い客に勧めたのは大坂で買ったすしだったことになる。 「押ずし」である
先代広沢虎造の口演では、「八軒屋から伏見へ渡す渡す船・・・(中略)・・・これへ石松さんが乗り込んで・・・(中略)・・・大坂本町橋名物の押しずしを脇へ置いて酒を呑み、すしを食べ・・・」と、「押ずし」であることを明言している。
大坂で江戸前握りずしは売られていた 大坂に初の江戸風ずし(握りずし)屋ができたのが文政の終わりごろ(1820年代後半)。石松の金毘羅代参は文久のころ(1860年代前半)であるから、大坂本町で江戸風の握りずしが売られていても不自然ではない。 「にぎりずし」である 東京風の握りずしが大阪で広がったのは、明治15年ごろから本町の「鉄砲家」が売り出してからである。
広沢虎造の18番、森の石松が舟のなかで「江戸っ子だ、すし食いネェ」とやって大阪本町の大阪鮓を取り寄せる・・・・・。この 「鉄砲家」は本町きってのすし屋だから、自然この店が石松のすし屋だということになり、なかなかはやる。店に「石松大明神」も祀られている。主人いわく「石松の金毘羅参りは文久3年だから、開店と年代がひらくが、お客さまはムードで来て下さるのだから、そんな細かいことはどうでも良い。広沢さんには大いに感謝しています」と。
参考文献 篠田 統著 すしの本
遊郭と化粧笹
笹の葉
すし同士が接触するのを防ぐために置かれる笹の葉のこと。『守貞漫稿』(嘉永2年<1849>)にその記載があり、江戸ではクマザサ、京坂ではハランを好むとある。 笹にせよハランにせよ、単なる仕切りだけではなく、そこに職人の包丁の腕を見せるため、さまざまな細工きりが施された。これがいっそうすし盛りを豪華に見せる。
台屋(遊郭)のすし
この盛り付けを半ば悪用したのが、「台屋(遊郭)のすし」で、笹をたくさん使い、少ないすしで豪華に見せた。 虎が出る 「台屋から 虎の出そうなすしが来る」の川柳は、虎が出てきそうな竹薮さながらの笹まみれ状態を表現している。
遊廓とすし屋のあがり
すし屋のお茶あがりの意味
寿司屋では煎じたばかりのお茶(番茶や煎茶に湯を注ぐ)のことを「あがり(上がり花)」と言う。
♪「娘18番茶も出花・・」 花柳界、遊郭では客が出入りする際にはお茶を出していた。
一番最初に出すお茶のことを「お出花」、一番最後に出すお茶を「上がり花」
あがりは、元々、遊郭の言葉で「上がり花(あがりばな)」の略。
「お茶を挽く(茶の葉をひいて抹茶を作る。)という言葉は、客のつかいない遊女や芸者が暇を持て余していることを意味するため、郭では「お茶」を忌み嫌い、「客があがる」という縁起を担いで「お茶」を「あがり」と言うようになった。
「あがり花」の「花」は「最初」のことで、「出たばかり」という意味の「出端」と「花」を掛けた、「出花(でばな)」と同様である。
すしの盛り込み
明治時代の1人前
桶や皿にに盛る時には七五三などの奇数が好まれたいう。大皿から小皿に取り分ける時も、七五三を意識した。食事としての1人前には3個というのは少ないように思うが、当時の握りの大きさから考えると5個・7個ぐらいで満腹にはなる。
「5カンのチャンチキ」
大正から昭和期には握り5個と細まき2切れを1人前とする風潮があった。これを「5カンのチャンチキ」と言う。合計7個だから、七五三の理屈には叶っている。
「重ね盛り」
箱ずしの時代からすしは重ねて盛るのが普通であった。明治時代でも、場合によっては昭和になっても、そうした
「重ね盛り」
習慣は根強くあった。桶や皿で中央を高くしてピラミッド状に盛ることを「杉形(すぎなり)に盛る」と言う
「台屋盛り」
遊郭出入りのすし屋では、少ない数で見栄えをよくするために、すしを重ねることはしなかった。こうした段重ねにしない盛り方を「流し盛り」もしくは「台屋盛り」(台屋とは遊郭のこと)と言った。元来があまり誉められた発想で盛られたものでないから、「堅気のすし屋ではやらない」とさえ陰口を聞かれ、店によっては1人前のすし盛りでもなるべく重ねて盛ったという。
「 流し盛り」
ところがいつのころからか、この流し盛りが一般的となり、現在では重ね盛りはすっかり陰をひそめてしまった。 その他の盛り 重ねない盛り方がすべてが流し盛りというわけではない。
「放射盛り」
中央に芯のような存在を作り、そこからすしを放射状に並べる。
「東西南北盛り」
多くはすしダネ別に置かれるが、1人前ずつセットにして放射状に並べる。これはどの方からも平等に「1人前」が取りやすい。
「水引盛り」
赤身のすしダネと白身のすしダネを左右に置き分ける。水引よろしく、赤い色を右側に配する。
「山水盛り」
重ね盛りと流し盛りを組み合わせ、器の中で山河風景を描く
お茶と湯のみ
すし屋のお茶
すし屋のお茶は粉茶とされる。一説には、すし屋がまだ低廉な食べ物であった時代、お茶にかかる経費を削減するために、最も安い粉茶を使ったのが起源だという。粉茶は玉露などの高級葉茶のように香りが立たず、また、旨味も少ない。それゆえにすしの持ち味を殺さないとして、価格とは別の理由でこれを使う向きもある。 すし屋の湯のみ 粉茶は熱い湯で入れねばならず、薄い湯のみ茶碗だと厚くてもてない。また、屋台での商売のころは、こまめに客に茶を供する手間を惜しみ、大きな湯飲みを用いたという。かくて、すし屋特有の分厚くて大きな湯のみ茶碗の伝統ができたらしい。
武士が食べなかった魚
江戸時代には、町人は食べたが、武士は食べられないものがあった。 それはコノシロ、マグロ、フグであった。 コノシロは「この城」と言い、語呂合わせ、「コノシロを焼く」「コノシロを食う」を「この城を焼く・食う」で武士は縁起が悪く、落城に通じるとされたのだ。 また「腹切り魚」といって切腹を命じられた武士の最後の食膳にのぼることが多かったのです。 ことからも、縁起の悪い魚とされ、 江戸幕府のお膝元ゆえ、江戸の方言の小肌にした。 マグロは、別名で「「シビ」と言う。「死日」に通じることから、いつ命をおとすかもわからない武士にとって、この名は禁句であった。それゆえにマグロは下賤な食べ物として食べなかった。 フグを武士は食べて毒に当たればお家断絶。武士が死ぬのは戦場であって、魚の毒などで死ぬのは武士にとってあるまじきことだったのだ。 そのため、武士のほとんどは、明治維新までフグの美味しさをしらなかったのである。 江戸中期から鰒をよく食べたのは「卑賎」と言われた庶民たちであり、その美味を体験していた。武士たちは頑健にも伝統的な食生活を墨守していたのである。 その頃は、鰒が一匹12文程度であり、安蕎麦一杯が16文であるのと比較すれば、いかに安価であるかが分かる。
参考文献 著者 日比野光敏 「すしの事典」
すしの1貫とは
鮨を数える単位を「貫(カン)」と呼びますが、なぜこの字か
なぜこの字が当てられるのかについていくつかの説があって、そのひとつに「銭さし一貫」が語源であるというものがあります。江戸時代、穴あき銭96枚の穴にひもを通してまとめたものを「銭さし百文」と呼び、本来は96文なのに100文として通用したそうです。
そしてこの「銭さし百文」を10個まとめて輪にしたもの、つまり960文が「銭さし一貫」(1000文)として通用していました。この「銭さし一貫」の重さは約3.6キロ「銭さし百文」の重さは360グラムほどあるのですが、この360グラムというのが当時の鮨ひとつの重量とほぼ同じくらいであったことから、小さいものを誇張する江戸っ子の洒落で「一貫鮨」と呼ばれ「貫」という単位の由来となったというのです。
まあ、鮨一個が360グラムというのはどう考えても大きすぎるとは思いますが、 いずれにしても江戸時代の鮨というのは想像以上に大きいものだったようです。 それが時を経て洗練されたとしても、明治の頃の握りはかなり大きかったと推察できます。