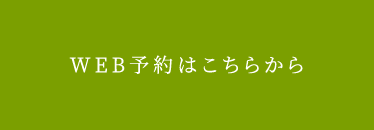鮨を知る
 UOTAKE SUSHI
UOTAKE SUSHI
地方のすし

2021年9月27日
近畿・中国地方
サンマずし(三重・奈良・和歌山県)
三重県南部と和歌山県東部の熊野灘沿岸および熊野川(新宮川)流域の郷土料理として知られる。分布域の北部は、奈良県南部の十津川村まで達する。サンマは別名サエラとも言い、「サエラずし」「サイラずし」とも称される。落ちアユも同じ方法で漬ける。
作り方
サンマは、冬場のものは脂が乗りすぎていて、すしには向かない。特に早ずしには、脂の抜けた夏から初秋にかけてのものが利用され、結果、秋祭りのご馳走によく上がる。発酵ずしはそれよりやや遅く、秋獲れたものを利用して正月料理になる。 発酵ずしの場合は サンマを背開きにして内臓を出し、約ひと月間、塩で締めておく。これを塩出しして、11月末から12月初めに飯に漬ける。サンマの腹に飯を抱かせ桶に並べ、飯をふりかけ、再びサンマを並べて、最後に落し蓋と重石をする。 約ひと月の発酵で食用となる。糀も酢も使用しない古式のナマナレである。桶や箱の中に敷くのは決まってシダの葉で、その青くさみが独特の風味を醸し出す。サンマの生くさみが気になる場合は、ショウガやユズのしぼり汁を用いるとよい。 早ずしの場合は やはりサンマを背開きにして内臓や背骨をとり、塩をしておく。これをザッと洗ってから酢に浸す。ここにすし飯を抱かせて、箱に詰めて押しをかければできあがる。サンマの臭みを取る場合にショウガやユズを使うのは発酵ずしと同じである。ただ、発酵ずしの多くが頭をつけてすしにするのに対し、早ずしの方は、頭を落としてからすしにすることが目立つ。ちなみに、頭を落としても「姿ずし」と呼んでいる。サンマずしが神饌 三重県熊野市有馬の産田神社では、神事の日参詣者に「奉飯」と称してサンマずし(早ずし)がふるまわれる。このすしだけは腹開きにするという決まりがある。しかも、背骨はつけたままである。産田神社は子宝・安産のかみで、うまれてきたこどまが「骨のある子」になるように、との願いが込められている。
雀ずし(大阪府・和歌山県)
タイの棒ずしではない。 大阪・和歌山を中心として、最近、京阪神一帯で「雀ずし」と称して売られているのは、大半がタイの棒ずしである。このすしはどう見ても雀を連想させるものではないからである。実際、このすしのルーツは、タイの棒ずしではなかった。 江ブナのすしと判明 江戸初期の『毛吹草』(正保2年<1645>ごろ)に、大阪福島の名物として「雀ずし」が挙がっている。この本には他の地方の名物ずしも紹介されていて、それらがいずれも発酵ずしであることから考えれば、この「雀ずし」もそうであったと想像される。 そしてそれは、寛文6年(1666)の『古今夷曲集』の
◆数おおふ 江鮒のうろこ 福島の 人は仕馴れて よいすずめ鮨 なる歌で、ほぼ証明される。「馴れる」という文言は発酵することを意味する。このすしが、江ブナ(ボラの若魚)のすしであったことも判明する。
名称の由来
「雀ずし」の名は、腹にご飯を一杯抱いて丸くふくらんだ胴体と、ピンと張ったヒレが雀に似ていたからだという。異説では、泳ぎだすような元気な姿が「吉原雀(遊郭の素見客)」の踊る姿に似ていたからだともいう。江ブナを小ダイに換えた 天明元年(1781)、雀ずしが仙洞御所の御用になった。その折、調整役を受けた魚屋が、江ブナでは生臭く皮も固かろうという理由で、大阪近海の淡路島や加太の海でよく獲れた「チヤリコ」と呼ばれる小ダイに換えた。以来、「雀ずし」は小ダイを握ったすしになった。それでも、魚の尾びれを張って握ったご飯を抱かせ、雀の形に似せたものだった。 現在の「雀ずし」 ところが近年、小鯛の水揚げが少なくなったのと、獲れても1尾一尾を下処理する手間がうとんじられたのであろう、小ダイの姿ずしは作られなくなってしまった。現在「雀ずし」の名で昔ながらの「握りずし」を売っている店もあるが、これなどは例外中の例外で「雀ずし」と言えば、大ダイのおろし身を貼った棒ずしになってしまった。しかも「握りずし」を売っている店でさえタイのおろし身を使っており、ヒレをたたせることはない。
アユずし(三重県)
特徴
伊勢地方の宮川流域で見られるナマナレ。冬場の料理である。木下健次郎は、近江のフナずしと並んで「支那の鮓に類似せる物」と表した(大正14年<美味急真>)が、形態的には、「魚+飯+塩」で構成されつつも(ユズの葉を入れることもある)ご飯を食用とする古式ナマナレである。
作り方
アユは10月末の落ちアユで、内臓を出し、エラやウロコをとって塩漬けしておく。11月末に塩出しして、すしに漬ける。ご飯は冷やしてからアユの腹に詰め、このとき、手水はあまりつけない。約ひと月ほどで食べられる。宮本神社への奉納 宮川流域のアユといえば、伊勢市佐八の宮本神社へ正月2日奉納が今でもづっと続き、献上用アユずしは当番が責任を持って準備し、祭礼の当日、白装束の男たちによって、他の供え物ともに神前に奉納される。 現実に、毎年元旦には、宮本神社から伊勢神宮内宮へアユが献上されたという記録(『内宮年中神役下行記』平安末~鎌倉の成立か?)が残っている。 フナずし(滋賀県) 現存する唯一のホンナレ 。
釣瓶ずし(奈良県)
室町時代のアユの発酵ずし
①釣瓶型をした曲げ物容器に漬けたアユの発酵ずしで、現在では早ずしに姿を変えているものの、その名称は下市町に実在しており、伝承の沿革が確認されるすしの中では最古のすしとも言える。
②このすしが文献に挙がるのは室町時代で、現段階では『石山本願寺』の天文22年(1553)11月17日の記録に「瓶鮨」とあるのが初出である。江戸時代には貴人御用となり、承応~万治年間(1650年代)に仙洞御所へ初献上。宝暦(1751~64)のころには、紀州徳川家を通じて、毎年4月と5月に将軍家献上することが決まっていた。仙洞御所への献上役に下命されたのが、下市の名家、「弥助」家であった。現在、下市町で「「釣瓶ずし」を調整販売している料理旅館「弥助」は、その末えいに当たる歌舞伎や浄瑠璃にも登場 延享3年(1746)に完成した竹田出雲の『義経千本桜』には、源氏に破れた平維盛をかくまう役どころとして、このすし屋が登場する。
あらすじ
吉野山中をさまよっていた維盛は、釣瓶ずしを商うすし屋の弥助に遭遇する。弥助は、かって維盛の父重盛に恩義を受けていた人物で、自ら家に作男として維盛を招き入れ、家族にも内緒で、敵の目を欺くことにした。この時、弥助はその名を維盛に譲り、自名を弥左衛門と改名する。 維盛は、いつしか弥左衛門の娘お里と恋仲になり、祝言を上げる運びになるが、その前夜、維盛を案じて吉野を訪ね歩いていた妻子と再会する。すべてを悟ったお里は、父とともに維盛一家の逃亡を手助けする。しかし、お里の兄で名うての厄介ものである権太が維盛の正体を聞きつけ、維盛の身柄を源氏の追っ手に引き渡すと宣言。一足先に家を出た維盛たちの後を追い、やがて「維盛の首を取り、妻子は生け捕りにしてきた」と帰ってきた。 居合わせた源氏方の梶原景時、首の入ったすし桶と妻子を引き渡した権太は、褒美をもらうが、逆上した弥左衛門に斬りつけられてしまう。死に際権太が言うには、桶の中の首は、あらかじめ弥左衛門が準備しておいたもの、差し出した妻子は自分の妻子だという。はたして、維盛一家は元気な姿で現れる。権太は改心し、わが身の家族と引き替えに維盛を守ったのだった。 その後、首と妻子を連れて行った梶原も、すべてを承知の上で維盛一家を見逃したことも判明。維盛は一人出家するとて、吉野を後にする。
「すしの日」の制定余談
平維盛が弥助と改名した日が11月1日だとされ、これが現在、全国すし商生活 衛生星同業組合が定める「すしの日」になっている。
「弥助」家の足跡 このすし屋の弥助(後の弥左衛門)のモデルとなったのは、仙洞御所への初献上から数えて7代目の弥助らしい。そのころには御所御用の看板が相当効いてか、かなり羽振りだったようである。その後江戸にも出店し、さらなる営業展開を試みた。実際、商売も当たったようで、江戸でも「弥助」の名前は知れた。後に、「弥助」「釣瓶」吉野」などの屋号を持つすし屋が増えたのも、だからこそである。 しかしながら、8,9,10代目の弥助が相次いで亡くなると11代目弥助は江戸の店を売却したりした。この時弥助家は相当に没落しており、御所の御用も危ない状況であった。ついに下市の家屋敷を手放し、享和2年(1802)、江戸に戻る。嘉永年間(1848~54)に、何代か後の弥助が下市の家屋敷を買い戻し、その後は、歌舞伎・浄瑠璃で高まった名声も後押しして、商売が軌道に乗ったらしい。これが現在の「弥助」家のようだ。現在は早ずし 貴人の御用にもなり、また芝居の舞台にも上がった釣瓶ずしは、ほんの20年足らず前までは、発酵ずしのかたちで作り続けられていたものの、時流に合わないという理由から早ずしに改められて、新たな「釣瓶ずし」となった。
昔ながらの発酵ずしの作り方
アユは吉野川のアユ。吉野のアユは腹に「桜の型(赤い斑点)」がある。6~10月のアユがよい。腹を出し、水洗いしてかなりきつめの塩加減で塩漬けする。期間はひと月以上で、1年間持たせることもできる。すしにする前に塩出しし、背骨を手ではずす。塩が強すぎる場合は2度に分けて塩を抜く。その後。さっと酢に浸し、水気をとってご飯を抱かせる。これを竹皮で敷いた桶に並べ(アユの背が下になるよう)、間にご飯をはさみながらアユを重ねる。詰め終ったらご飯でふたをする。 ただし、これは十分発酵させる場合で、5~6日で食べる場合は、アユの間や上部にご飯を置かない。最後に竹皮で覆い、ふたを落とす。桶は「締め木」なる木枠にはさみ、クサビでふたを桶の中に押しつけながら、クロフジ・クズフジの蔓(つる)で全体を締めまわす。これが仮締めで、しばらくしてからさらに蔓を締め付け、本締めとなる。10日ぐらいで発酵臭がただよい、ほどよく馴れる。「弥助」家の河合翁談 製法を教えてくれた「弥助」家の河合翁もそうだったが、土地の人はアユといわず、アイと発音する。
さればこそ『義経千本桜』の
◆愛に愛もつ鮎の鮓 なる一節が生きてくる。
サバずし(京都府)
サバ街道
海から距離のある京都の街には、サバは三方面から運び込まれた。ひとつは北サバと呼ばれる若狭産のサバで、近江湖北を経て京に向かう道は「サバ街道」とも称される。今ひとつは、出雲・石見あたりの産で、瀬戸内経由で淀川を上がってくる西サバ。残るひとつは紀州熊野のサバである。京の人々は、このうち若狭のサバをとくに好んできた。
作り方
京の町屋で祭りに欠かせないのがサバの棒ずしである。サバは、塩サバをよく洗い、骨を除いて酢に浸す。身が白くなったら酢から上げ、表皮を剥き、身の中ほどの厚い部分を削ぎ取る。この時、切り口がまだ赤身を帯びているくらいの方が、生臭みは少ない。すし飯をサバの大きさに合わせて四角く握り、サバ身を貼る。尾の方は身が細くなっており、ご飯が見えてしまうので、先にそぎ取った身をここに置く。布巾などで全体を包み、成形する。これを竹皮で包み、まとめて押しをかける。ひと晩おくと、味がなじむ。
まつぶたずし(京都府)
特徴
北丹後ちほうの、海岸部よりやや内陸の地域で見られる。「まつぶた」とは餅などを並ぶておく浅い木箱のこと。ここにすしを作る。基本的には混ぜずしであるが、まつぶたの中で固めて、ヘラで切り出すところが、他には例の少ないユニークなところである。
具 オボロ・カンピョウ・シイタケ・高野豆腐・カマボコ・フキ・キヌサヤなどである。 オボロは、昔は焼きサバから作ったものだが、今ではサバ缶を使うことが多い。鍋で醤油と砂糖を加えながら炒り煮にする。シイタケ・カンピョウ・高野豆腐など甘辛く煮付ける。フキやキヌサヤは色合いよく塩ゆでにする。このほかには、錦糸卵・紅ショウガ・木の芽なども使う。
作り方
まつぶたにすし飯を敷き、カンピョウや高野豆腐・おぼろなどの煮物を散らす。 その上にまたすし飯を乗せると、その上面が仕上がりの表面となる。ここはすべての具を彩りよく撤き散らす。最後に手で軽く押さえ、すしを平らにならす。食べる時は、特性の木ヘラを突き刺し、すしを切り分けて小出しする こうした食べ方は江戸時代の料理本『名飯部類』の静岡県の「切りだめずし」 「おこしずし」「すくいずし」ににてると記した。すなわち、このすしも、箱ずしから混ぜずしへの移行期の形態だと言える。
蒸しずし(京都府・大阪府)
特徴
混ぜずしを蒸したもの。「蒸しずし」の幟旗を上げた店先で、蒸籠から勢いよく湯気があがるのは、京都・大阪に冬の風物詩である。「ぬくずし」とも言う。もとは重箱ごと蒸し籠に入れ、そこからすくい出したらしいが、今では茶碗などの銘々器に詰めて蒸している。出前しやすいように改善したのだという。 すしは大半が冷たい食べ物であるが、享和2年(1802)の「名飯部類」に「あたためずし」というのが出ている。ただしこれは、熱いすし飯に具を混ぜ、保温しておいて暖かいうちに食べるというもので、「暖める」わけではない。積極的に加熱するのは明治初めに大阪で考案されたというが、俳人の内藤鳴雪が慶応年間(1865~68)」に京都新京極でこのすしを食べたという記録がある。(大正11年<1922>「鳴雪自叙伝」)。期限はもう少し古いようだ。具 混ぜ寿司の具は、昔はシイタケ・すだれ麩・焼きアナゴ・クリ・キクラゲ・おぼろなどであった。彩のためキヌサヤや錦糸卵は、蒸しあがってから上に乗せると色が劣化しない。また、同じ錦糸卵でも大阪ではすり身を入れて焼くが、京都で入れずに焼くという違いがあった。 器 大正のころは、底に穴が空いたものがあった。冬場の芝居見物の昼食は蒸しずしというのが普通で、時分になると客がどっと押し寄せた。多数をさば切るために、効率よく熱が回る「穴あき茶碗」が考え出されたという。あわて者が、食べた後の茶碗に茶を注いで失態を演じたという笑い話がある。
アユずし(兵庫県)
特徴
但馬地方の香住町、矢田川中流域で、正月料理として作られる。発酵ずしで、古式ナマナレである。
作り方
アユは、夏場のがよいが、なかなかまとまって獲れないので、九月中下旬の落ちアユを使う。これを腹割して内臓を出し、塩漬けにする。翌日、アユを塩水で洗いながらエラなどを取る。ご飯は冷めている方がよいと言う人もあれば、暖かい方がよいと言う人もある。ともあれ、アユの腹に詰め、アユを桶に並べてゆく、一段終わったら上からご飯をパラパラかけ、タデ葉も散らす。 これを繰り返し、最後はやや厚めのご飯の層にして、竹皮でふたをし、クミワラ(わらを太く編んだもの)で桶の内側を密封しながら落し蓋と重石を置く。約ひと月で食べられるが、三カ月ほど経った正月ごろが食べ時で、重石効かせれば春まで持つ。
大阪ずし(大阪府)
名称
大阪府下では、各地で甘味の効いた箱ずしや混ぜずし・太巻きずしなどが家庭料理として伝承されており、その意味で、大阪のすし文化の特徴を述べることはできる。しかし「大阪ずし」とはこれら大阪の一般家庭のすしを総称する語というより、「東京の江戸前握りずし」に対する「大阪の箱ずし」を表現することの方が多い。 この名称はさほど古いものではなく、文政のころを越えることはない。江戸の握りずしが生まれる以前は「すし」といえば箱ずしがあたりまえでそれをわざわざ「大阪ずし」と呼ぶこともなかったからである。その後、江戸前握りずしの躍進とともに、呼び分ける必要が生じた。 箱ずしのことを、「こけらずし」とも呼び、室町文献にその名が見える。コケラとは木屑のことで、飯に混ぜ込む魚の切り身をそう見立てたのであろう。
すしの作り方が一変
江戸では握りずし以後、箱ずしは廃れたが、京坂では箱ずしやこけらずしは残った。こけらずしは、文政の末か天保の初め頃に大阪心斎橋南に開店した「福本」なるすし屋が、具の卵焼きやタイ・アワビの刺身を、従来に2倍近い二分(約6ミリ)の厚さにした。これが好評を得てこの店ができて以後は,すしの作り方が一変した。 「福本」は、一日ないし二日ほど重石で押して置いた従来の方法を,手押しに改めもしたという。(明治25年ごろ『浪花百事談』)。そのすしが,現今の大阪ずしの直接的なルーツであることは言をまたない。吉野寿司が更に具の洗練 明治20年代に、船場の「吉野寿司」が、これをさらに洗練した。上置きの具を酢締めのタイ・締めサバ・塩ゆでエビ・焼きアナゴ・厚焼き卵などに改め、これを二寸六分のすし枠の中に配置した。いわば、二寸六分の中に会席膳凝縮されているようなもので、程度の差こそあれ、今日の大阪ずしの具は、ほぼこれに準じている。
「こけらずし」の呼び名
上置きの具を貼る際、隣の具にごくわずか重なるように置く。これはコケラ(この場合「コケラ板」すなわち屋根葺き板のこと)を葺くのに似ている。よって、このすしを「こけらずし」と呼ぶのだと聞いた。今のコケラには、「木屑」の意味は失せているようだ。
江戸前にぎりずしとの異なる特徴
江戸前にぎりずしのように、「製して、すぐに食べる」という動きに走らなかったことにある。しっかり押しをかけ、かつ、しばらく置いた方が具とご飯がなじんで風味は増す。それゆえ、江戸前にぎりずしがすしダネの下処理を放棄して刺身をそのまま乗せるようになったのとは対照的に、具の下処理を怠らぬやり方が伝承される。合わせて酢に砂糖を効かせろのも、その方が日持ちしやすいからであろう。
店のカウンターで職人と向き合って食べることも少ない。したっがって、江戸前握りずしのカウンターで見かける、「すし通」ぶった食べ方やみょうな作法めいたものは生まれてこなかった。逆に、店のすし折を弁当に持って出掛けたり来客に持ち帰らせたりする習慣が、大阪では至極自然に息づくことになる。
バッテラ(大阪府)
本来はサバずしではなかった 現代では、棒ずしに仕立てたサバずしの代名詞のように用いられることばになっている。「サバずし」と「バッテラずし」の違いは「身が薄くて値段が安いのがバッテラだという。 いつ頃からこういう区別ができたのか、バッテラずしは、本来、サバずしではなかった。
名前の由来
明治の27~28年(1894~95)ごろ、大阪順慶町の「鮓常」なる店が、当時安かったコノシロを2枚におろし、その半身をすし飯に乗せて売り出した。このすしは、尾の方に行くにつれて魚身が細くなるから、下のすし飯も細らせてあった。これを見た客の一人が「バッテラ(オランダ語でボートの意味)に似ている」と言ったことから、バッテラずしの名前がついたという。その後。コノシロが値上がりしたのでサバヘと変わり、すしも棒ずしになったが、名前だけはそのまま残ったらしい。
サバずし(大阪府)
北摂のサバずし
海から遠い摂津の山間部でも秋祭りにはサバずしが作られてきた。 北摂ノサバずしは、以前は尾頭をつけた姿のままのすしであった。今は、塩サバを3枚におろした半身を棒ずしにすることが多い。すし飯は甘さを控え、砂糖を入れない家もある。このご飯を棒状に握り、サバを置いて布巾などで形を整えた後、竹皮で包んで縛る。これをすし箱に詰めて軽めの重石を置き、翌日まで置くと味がなじむ。
「松前ずし」と「サバずし(棒ずし)」の違い
松前とは北海道の松前のことで、かの地で採れるコンブを表わす。すなわち、サバずしの上に昆布を貼ったものが「松前ずし」である。明治の終わりごろ「丸萬」なる店が黒板コンブを貼ったサバずしを考案して好評得たのが始まりで、もとはこの店の登録商標であった。その後名称をめぐるトラブルがあり、「丸萬」だけが「松前ずし」の名前を使い、他店は「コンブ巻き」と称することで一段落したが、それが遵守されていないことは現状に明らかである。 また、黒板コンブでは時間が経つとぬめりが出ることから、次第に白板コンブになっていった。ともあれ、「サバずし」と「松前ずし」を呼び分けるのであれば、それはコンブの使用の有無が基準となるべきである。しかしながら現実には「サバずし」にもコンブが置かれていたりする。さらに「バッテラずし」もあいまって、大阪のサバずしの区分は、たいへん不明確なものとなっている。
サバずし(和歌山)
特徴
和歌山県のサバずしには、発酵ずしと早ずしの2種類がある。 発酵ずしは、日高・有田地方の、とりわけ平野部で秋祭りのご馳走としてよく作られる。単に「なれずし」とも呼ばれる、典型的な古式ナマナレである。 一方、早ずしは紀北地方でしばしば見られる。一部には姿ずし・棒ずしにもするが、概して箱ずしである。
発酵ずしの作り方
①多くの秋祭りは十月で、そのひと月ほど前に塩サバを準備しておく。これはサバを背開きにして内臓や骨を取り、よく血抜きしてから、約一カ月間、塩漬けにするのであるが、市販の塩サバを購入する家もある。
②すし漬けは、塩サバの塩抜きから始まる。桶に水を張り、塩サバを入れて塩気を出す。水は2~3回取り替えなければならない。ほどよく抜けたら、水気を切っておく。ご飯は、やや固めに炊く。粘り気があるので、古米の方がよいとされている。炊き上がったらあら熱を取って、辛目の握り飯ていどの味となるよう塩を混ぜ、さらに冷ます。これを、サバのみに合った大きさのニンニコ(握り飯)にする。
③開いたサバにニンニコを抱かせ、魚の形に戻るように形を整えると、外からバランやアセ(ダンチク)の葉を巻きつける。最後にシユウロ(シュロ)の葉を裂いたもので縛り、サバを包んだ葉を止める。これを深底の桶に並べ、一段終わったら、バランやクマタカ(カンナ)の葉で仕切り、さらにサバを並べる。何度も繰り返して桶が一杯になったら、落としぶたをして重石をかける。 約ひと月後のできあがりは、ご飯が固く締まっており、外見上は酢を使った早ずしとさほど違いがない。つまり、ご飯の比重は大変重いわけで、冒頭で「典型的ナマナレ」と記したのはそのためである。早ずしの作り方 サバを三枚におろして塩で締め、その後水洗いして、甘めの酢に浸ける。酢で身が締まったら皮をはぎ、そぎ切りにする。このサバ身を、こぶし大に握ったすし飯の上に貼り、すし箱の中に並べてゆく。深底の大箱であれば一段並べ終わったところで仕切り板もしくはバレン(バラン)を上置きし、さらにすしを並べる。これを繰り返し、箱一杯になったら落とし蓋をして重石を置く。翌日になれば味がなじんで美味になる。
岩国ずし(山口県)
規模・豪華さは全国屈指 地元・岩国では「角ずし」と呼ばれるが、一般には「岩国ずし」の方が通りがよい。非常に大掛かりな箱ずしで、その規模や豪華さは全国屈指と言えよう。すし箱は、3升入りのものがよく普及しており、他に5升入りや1斗入りのものまである。冠婚葬祭のご馳走にはしばしば作られ、大皿に豪華に盛り付けて供される。 具となるのは 岩国名産のレンコン(酢バス)のほか、甘辛く煮付けたニンジン・シイタケ・ゴボウ・酢締めした白身魚、錦糸卵、赤寒天(乾燥したままのものをちぎって使う)、青み(シュンギク・サンショウ・青ジソ)などである。
高知県の「こけらずし」の製法 3升ものご飯を収める箱となれば、当然、底も深い。こうした場合、すし飯と具を何等分かにし、ご飯を敷いて上に具を置き、平らにならした後、仕切り板を置いて、その上にまたご飯と具を乗せる。といった風に、板で仕切りつつ、箱の中にすしの層を重ねるという方法を採ることがよく見られる。 「岩国ずし」の製法がユニーク 仕切り板を用いない。飯や具を何等分かにすることは同じだが、板に相当するものがバショウやハスの葉になっている(古くはバショウで、後にハスがよく使われるようになった)。このため、すしを箱から抜き出して切り分ける際、他所では仕切り板をはがして、すなわち、すしを一層ずつに分けて切るところを、ここでは全層を重ねたままで切ってしまう。分厚いままで小さく切り分け、その後、葉の部分で層を分かつのである。よって、相当大きな包丁が必要となり、すし切り専用のものがある。
「殿様ずし」の異名 今でこそ一般家庭でも作られる岩国ずしだが、明治期まではごく一部の武家階層でしか食べられず、「殿様ずし」の異名もあったという。 規模・豪華さは全国屈指 地元・岩国では「角ずし」と呼ばれるが、一般には「岩国ずし」の方が通りがよい。非常に大掛かりな箱ずしで、その規模や豪華さは全国屈指と言えよう。すし箱は、3升入りのものがよく普及しており、他に5升入りや1斗入りのものまである。冠婚葬祭のご馳走にはしばしば作られ、大皿に豪華に盛り付けて供される。
具となるのは 岩国名産のレンコン(酢バス)のほか、甘辛く煮付けたニンジン・シイタケ・ゴボウ・酢締めした白身魚、錦糸卵、赤寒天(乾燥したままのものをちぎって使う)、青み(シュンギク・サンショウ・青ジソ)などである。高知県の「こけらずし」の製法 3升ものご飯を収める箱となれば、当然、底も深い。こうした場合、すし飯と具を何等分かにし、ご飯を敷いて上に具を置き、平らにならした後、仕切り板を置いて、その上にまたご飯と具を乗せる。といった風に、板で仕切りつつ、箱の中にすしの層を重ねるという方法を採ることがよく見られる。
「岩国ずし」の製法がユニーク 仕切り板を用いない。飯や具を何等分かにすることは同じだが、板に相当するものがバショウやハスの葉になっている(古くはバショウで、後にハスがよく使われるようになった)。このため、すしを箱から抜き出して切り分ける際、他所では仕切り板をはがして、すなわち、すしを一層ずつに分けて切るところを、ここでは全層を重ねたままで切ってしまう。分厚いままで小さく切り分け、その後、葉の部分で層を分かつのである。よって、相当大きな包丁が必要となり、すし切り専用のものがある。「殿様ずし」の異名 今でこそ一般家庭でも作られる岩国ずしだが、明治期まではごく一部の武家階層でしか食べられず、「殿様ずし」の異名もあったという。
サバずし(鳥取県)
特徴
千代川上流域の正月料理として作られる発酵ずし。魚・飯・塩の構成材料に糀が加わった改良型ナマナレである。もとはこの川で獲れるアユを漬けたのであるが、アユが獲れなくなってからは海魚に変わり、サバやシイラが漬けられるようになった。
作り方
サバも志伊良も、山奥まで運ばれてくるために、しっかり塩を効かせた「食い塩」になっている。サバは半身におろし、またシイラは大ぶりの切り身にして、やや辛目に塩出ししてから使う。ご飯は人肌に冷まし、等量の糀を混ぜる。これと、魚とう桶の中に交互に重ねてゆく。落し蓋と重石を置き、約2カ月間ほどで糀の甘味が効き出す。 食べ方は古いホンナレの要素 食べるときはご飯をこそぎ落として魚身だけにし、刺身のように薄切りにする(これを「はやす」と言う)。このように、ご飯をこそぎ落とすのは古代の食法で、現在のわが国には、滋賀県のフナずしなどごくわずかな事例しかない。
しかも、このサバやシイラのすしはあぶったり焼いたりして食べることもある。すなわち、すしの完成をもって調理の到達点としない場合もあるわけで、この場合は加熱という二次加工を経て初めて調理の完了となる。これは、フナずしにはない特徴である。材料構成こそナマナレの改良型であるが、食べ方としてはすこぶる古いホンナレの要素を持っている。 すしの原型に通ずる 「ほぞんしょく」を「素材の貯蔵方法」と考えるならば、これにさらに調理を加えることは自然なことと認められよう。すしの発祥地と目される東南アジアにおいては、すしが加熱調理されることもめずらしくはない。
平安期にあったイノシシやシカのすしも、生食したとは思えない。二次加工の可能性を持っているという点で、このすしはすしの原型にも通ずるものがある。
特徴
千代川上流域の正月料理として作られる発酵ずし。魚・飯・塩の構成材料に糀が加わった改良型ナマナレである。もとはこの川で獲れるアユを漬けたのであるが、アユが獲れなくなってからは海魚に変わり、サバやシイラが漬けられるようになった。
作り方
サバも志伊良も、山奥まで運ばれてくるために、しっかり塩を効かせた「食い塩」になっている。サバは半身におろし、またシイラは大ぶりの切り身にして、やや辛目に塩出ししてから使う。ご飯は人肌に冷まし、等量の糀を混ぜる。これと、魚とう桶の中に交互に重ねてゆく。落し蓋と重石を置き、約2カ月間ほどで糀の甘味が効き出す。
食べ方は古いホンナレの要素 食べるときはご飯をこそぎ落として魚身だけにし、刺身のように薄切りにする(これを「はやす」と言う)。このように、ご飯をこそぎ落とすのは古代の食法で、現在のわが国には、滋賀県のフナずしなどごくわずかな事例しかない。しかも、このサバやシイラのすしはあぶったり焼いたりして食べることもある。すなわち、すしの完成をもって調理の到達点としない場合もあるわけで、この場合は加熱という二次加工を経て初めて調理の完了となる。これは、フナずしにはない特徴である。材料構成こそナマナレの改良型であるが、食べ方としてはすこぶる古いホンナレの要素を持っている。
すしの原型に通ずる 「ほぞんしょく」を「素材の貯蔵方法」と考えるならば、これにさらに調理を加えることは自然なことと認められよう。すしの発祥地と目される東南アジアにおいては、すしが加熱調理されることもめずらしくはない。平安期にあったイノシシやシカのすしも、生食したとは思えない。二次加工の可能性を持っているという点で、このすしはすしの原型にも通ずるものがある。
シロハタずし(鳥取県)
ハタハタのおからずし
鳥取県賀露の漁港な4月は、押し寄せるシロハタ(ハタハタ)の豊漁になる。春祭りにはこれのオカラずしを作り、客にふるまい、持ち帰らせたものだ。
作り方
シロハタは背割りにして腹を出し、よく水洗いしてからしっかり塩に漬ける。一晩おいて翌日、半日ほど塩出しし、その後またひと晩、甘酢に漬ける。オカラにも甘酢をあてて、麻の実をふり混ぜながら空炒りする。シロハタにオカラを詰め、魚の形になるように整えて、これを木桶に並べる。一段並べたらオカラを散らし、また魚を並べる。一杯になったら最後にオカラをふり、落し蓋をして軽く押す。 翌日から食べることができるが、美味なのは3日目くらいとされる。寒い時期に作るとひと月ほど持つといい、こうなると、半ば発酵ずしの要素をもっている。
おまんずし(島根県)
オカラの姿ずし
石見地方の、比較的海に近い地方でよく作られる。オカラを使った姿ずしで、魚は、かってはサバがよく使われたが、最近は家族が減ったせいか、イワシのすしがよく作られている。昔から、秋祭りの食卓をにぎわしてきた。 作り方 魚は開いて骨と内臓を取り、塩で締めた後に酢で締める。オカラは甘酢で味をつけ、麻の実と刻みショウガを混ぜて空炒りする。これを熱いうちに魚の腹に詰め込み、布巾などで成形する。作りたてから食べられ、そのため「熱いおまんずし」というのもある。これはこれで、好む人がいる。 風変わりな名前の由来 おそらく江戸の「おまんずし」が起源ではないかと思われる。江戸の「おまんずし」は、巷説(ちまた)では、宝暦の初めごろ(1750年代)、上槇町(日本橋南通)で長兵衛なる男が始めたすし屋である。後に紀伊国屋と称したが、店主の妻の名前が「おまん」で、時の人気役者で女形の瀬川路孝(菊の丞)に似た美人として誉れ高かったため、「おまんずし」の名前は知られていた。
「おまんずし」はオカラずしの代名詞
この店は、数日間漬け込む半発酵ずしを商っていたようであるが、いつのころからかオカラのすしを売り出し、これが評判となった。少なくとも天明年間(1780年代)までには、オカラずしといえばこの店が連想されるまでになっていたらしく、後続の店でも、オカラずしを売り物にする店は、「おまんずし」の名を冠したりした。こうして、ついには「おまんずし」はオカラずしの代名詞にまでなった。石見のオカラずしが「おまんずし」と呼ばれるのはこうした背景によるものであった 。
ばらずし(岡山県)
贅沢な郷土料理 岡山県の郷土料理を代表するといっても過言ではない。それほどまでに著名になっていた。全国でも屈指の豪華な混ぜずしで、その贅沢さは「すし一升金一両」とまで称される。「備前の食い祭礼」と言う言葉どうり、祭りのすしには金を一両かけても惜しまないという意味である。もともとは平野部における祭礼・人寄せのご馳走で、それゆえに「祭りずし」ともよばれてきたが、この「祭りずし」の名を全国区にしたのは岡山駅弁であろう。百貨店などの駅弁大会などでさまざまな「祭りずし」が販売されている。その贅沢さが日本中に知られるにつれて、「岡山ずし」と言う名前も生まれた。
岡山の風土を表現 その豪華さは、岡山という風土を実によく表している。米は自慢の備前米。肥沃な備前平野から生産される豊富な野菜。背後に控えた中国山地からはキノコ類や山菜。そして、目の前に広がる瀬戸内からは、文字通り近海の海産物。これらをまとめてすしの入れるのであるから、他所の人々からうらやましがれるようなすしができあがる。一例をあげれば、すし飯にはニンジン・シイタケ・カンピョウなどを甘く煮付けて混ぜいれ、上には錦糸卵を敷き、その上に、サワラ・イカ・エビ・アナゴを上置きし、さらに、キヌサヤや紅ショウガで彩りをつける。大きな飯切りに作れば圧巻である。
発祥伝説 岡山城主の池田光政は、領民の贅沢を戒めるため、「一汁一菜」の令を発した。つまり、食事の際の副食は、汁物を除いて一種類に限るというのである。日常においても領民もこれに従っていたが、年に一度の祭りの日にもこれを適用されてはたまったものではない。そこで、「せめて祭りの日くらいはおかずの品数を増やしてほしい」と願い入れたが、藩はこれを拒否。やむにやまれぬ領民側がひねった知恵が、飯の中に山海の味覚を混ぜ込んでしまう方法であった。これならば、おかずの皿数は増えず、「副食」にはカウントされないというわけだ。かくて生まれたのが、具がいっぱい入ったばらずしである。重箱に詰める場合は、底に豪華な具を敷き、上に質素なすし飯を置く。表面的には質素に見えるわけで、これを「もぐりずし」と呼ぶ。
現実には疑わしい話 こうした話は観光協会などにも紹介されて、現在最もよく語られるものであるが、現実には疑わしい。ひとつには、池田光政(天和2年<1682>没)の時代は、酢を使ったすしが出始めたころであった。少なくとも混ぜずしなるものが生まれていなかった。 現実に、昭和初期における一般家庭のばらずしは現在ほども贅沢ではなく、ここまで豪華なすしが庶民に許されるようになったのは、さほど古いことではない。すし一升に金一両を費やすことができたのは、限られた人たちだったようだ。
しばずし(広島県)
名前の由来
因島近辺で見られる。西日本ではめずらしい糀併用の発酵ずしで、瀬戸内では唯一。 別名「ジャコずし」とも呼ばれる。ジャコとは雑魚のことであろうが、雑魚は「取るに足らない小魚」ではなく、、「(種類を問わない)雑多な魚」と言う意味であろう。「しばずし」の語源は不明。 魚種は特定してない 実際、漬け込む魚は特定されておらず、タイ・キス・ママカリ・タコなどまとめて漬ける。到来物の塩ザケも漬けけてしまう。ここまで魚種にこだわらず、また、複数の魚を一緒に漬けてしまう作り方をするすしは全国でも類はない。ある意味では、非常に原始的な製法と言えよう。
作り方
時期は秋で、10月ごろの秋祭りに供される。入手できた魚を塩漬けにしておき、すし漬け前に塩出しする。これを、飯と糀、そして刻んだタデの葉とともに桶に入れ、重石をかけて、ひと月ほど発酵させる。 現今は魚だけを漬けるが、かってはマツタケやミョウガなどを入れたこともあるという。また、最近では飯の分量が減り、糀だけで漬ける人もある。
あずまずし(岡山・広島県)
名称の由来
ご飯代わりにオカラを使うものを指す。この名称は、岡山・広島両県の、主として海岸部での呼称のようである。 「あずま」の語源はは不明。「関東」「江戸」のことかとも解される。 オカラを使うのは節米のため 米を購入する漁村では、祭りのような特殊日でも、米は贅沢に使えるものではなかった。少しでも米を節約するために、飯とオカラを半々に混ぜ、あるいはオカラばかりで、合わせ酢をあててすしにしたのだという。
形態的には握りずし
形態的には握りずしとなるが、姿ずし系のものと握り飯系のものがある。
姿ずし系のすしの作り方
イワシやコノシロ・ママカリ・タナゴなどの小魚を頭のついたままで使う。魚は開いて内臓や中骨を取り、塩と酢で締める。オカラ(もしくはオカラとご飯の混合)は煮つけたニンジンやシイタケ・油揚げなどを細かく刻んで混ぜ(ただし、広島県側では、麻のみくらいしか入れないらしい)合わせ酢をうちつつ炒り煮にする。これを、俵型に握り、先の魚をかぶせ、手で握り直して成形する。
握り飯系のすしの作り方
一方の握り飯系のすしは、混ぜ込む具がやや多彩になり、高野豆腐・コンニャク・クロマメなどのほか、祝儀の時にはカマボコ・エビも混ぜる。これを握り飯にして、客にふるまう。この習慣は岡山県側では希薄で、どちらかと言えば広島県のものである。