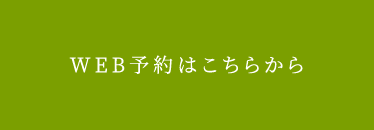鮨を知る
 UOTAKE SUSHI
UOTAKE SUSHI
地方のすし

2021年9月30日
北海道・東北・関東・甲信越地方
飯ずし(北海道・青森・宮城・秋田県)
同一材料構成のすしの総称 塩漬けした魚をダイコン・ニンジンなどの野菜とともに、飯と糀に漬けて発酵させたすし。 魚はサケ・ホッケ・ハタハタが顕著で、そのほか、ニシン・サンマ・イカなどもよく用いられる。青森県津軽地方ではカワハギのすしを漬けたというし、秋田県の八郎潟では潟魚のカレイやフナも漬けた。 同型の材料構成を持つすしは 秋田県のハタハタずし・山形県の粥ずし・富山県と石川県のカブラずし・石川県と福井県のダイコンずし・岐阜県の寝ずしなど北海道から北陸にかけての日本海側で見られる。 東北地方でも岩手県・宮城県など太平洋側では発酵ずしの慣行はほとんどないが、例外的に、岩手県湯田地方にハタハタのすし漬けが、宮城県亘理地方にサケの飯ずしが伝承されている。
イズシの名称
この材料構成を持つすしの総称として「イズシ」の語が使われるのは、やはり飯ずしの存在が大きいからであろう。この名称は北海道・青森県・宮城県・秋田県のほか、新潟県北部でも使われている。ただし青森県の一部と秋田県においては、ハタハタを使ったものだけは「ハタハタずし」と称して「飯ずし」とは呼ばない。
製法
魚はあらかじめ塩漬けしておく。サケはもちろんニシン・ホッケなども切り身にするが、サンマやイかは内臓を取るだけで丸ごと漬けることがある。 この魚と、飯・野菜を桶に層に重ね、重石をかける。約ひと月で食べられるようになる。糀は飯に混ぜておく場合と、桶に飯を詰める際に上からふりかける場合の両方ある。飯の分量はさまざまであるが、概して野菜を使わない発酵ずしに比べて少なく、中にはほんの申しわけていどにしか入れない家もある。
赤ずし(秋田県)
名称の由来 主として県北から横手地方の山間で伝承されている料理で、一見するとキュウリとシソの混ぜずしであるが、基本的に酢は使わず、酸味は飯とキュウリの発酵から生じさせる。全体にシソから出る赤みがまわり「赤もの」「赤まんま」などとも呼ばれる。「けいとまま」の別称もある。
また「盆ずし」とも称されるのは、これが盆の料理であるからで、盂蘭盆の時にはハスの葉にこのすしを盛って、仏前や墓前に供える家庭もある
作り方
飯は餅米で炊き、少し冷まして桶に敷き、上にキュウリやカタウリ(シロウリ)の漬物を刻んで散らし、さらに少量の塩で揉んで赤シソの葉を散らす。この時、糀を混ぜる場合もある。また、漬物は古漬けの方がよいと言う人もある。これを数回重ねて層を作り、最後に軽く重石をする。数日から一週間ほどで、ほどよく馴れる。
また、あらかじめ梅酢に漬けておいた赤シソを混ぜる場合もあり、この方法ならば、漬けてすぐに食べることもできる。漬ける際に砂糖を加えることもあるが、反面、作るときには甘味は一切加えず、食べるときに砂糖をかける人もある。
ハタハタずし(秋田県)
縁起のよい魚 民謡「秋田音頭」で八森(山本郡)の名物と歌われたハタハタは、表皮の柄が富士山に似ていることから縁起のよい魚とされ、、秋田の正月には欠かすことのできない。今でこそ地場ものは高級魚になってしまったが、かっての年末の秋田沖はハタハタ漁でにぎわい。
三百数十年も昔から名物 野菜とともにつける発酵ずしの代表格でもある。 江戸時代の俳諧の参考書『毛吹草』(正保2年1645>ごろ)で出羽名物として紹介されており、ハタハタずしの名声は少なくとも三百数十年も昔から確立していたことがわかる。「すべて元旦より2月朔日まで、飯ヰ祝ひの膳には鮓のはたはたを用る也」(文化11年<1814>『出羽国秋田風俗問状答』とも記録され、このすしがいかに地域に根づいていたかが知れるが、反面、佐竹家(秋田藩主)文書などいわゆる上流階級の記録にはほとんど挙がっていない。つまり、庶民に支持されたすしであったと想像される。
名称の由来
ハタハタずしには、1尾ぐるみすしに漬ける「全すし」と、切り身にして漬ける「切りずし」とがある。けれども昨今では、頭を落とした状態で漬けるものを「全ずし」と称し、尾頭つきで漬けるものは別に「姿ずし」と呼び分ける傾向がある。最も普通に見られるのは頭を落とした全ずしで、姿ずしは改まった席の皿付料理に用いられるほどである。
作り方
数日間漬けたハタハタを水で塩抜きし、糀を混ぜたご飯と、ニンジンやカブなどの野菜、コンブなどの海藻類とともに桶に詰め込んで、重石をかけて3~4週間発酵させる。漬け込みの際に塩抜きしたハタハタを酢にくぐらせるのは新しい技法である。食べるときは、生でそのまま食べるほか、軽くあぶることもある。通常は2月ごろまでに食べ終えるが、昔は、塩気をしっかりきかせて5月の田植えの時期まで持たせることもあったらしい。
現在でも消費が多い 近年は観光客相手に気楽に買える土産物になっている。全国的に発酵ずしが衰退に向かう中で、今でもこれほどまでに住民に親しまれているのは、数少ない例だと言える。
粥ずし(山形県)
名称の由来
山形県酒田市の豪商家の正月料理として伝わってきた発酵ずし。杓子ですくわなければならないほど飯が粥状に柔らかいのでこの名がある。
作り方
材料は、サケ・カズノコ・ハララゴ(サケの真子)などの魚類と、ニンジン・アオマメ・コンブなどの野菜海藻類と、飯と糀で、これらをまとめて桶に漬け込んでしまうこともあるが、多くはあらかじめ飯と糀を合わせて寝かせておき、粥状の漬け床を作ったところに他の材料を漬け込む方法が採られている。漬けてからおよそ2週間からひと月半までが食べごろである。
酒の肴
漬け込みの際に酒を混ぜることもあり、その年にできた新酒を使うのを習いとしていた家もある。実際、酒とは相性がよく、食事というより酒肴に近い存在で、かっては年末年始の到来客へのふるまい酒とともに供されたという。
けれども、現在では作る家庭はめっきり減ってしまった。入ります。
にしんずし
特徴
会津地方の発酵ずしで、正月用に作られる。山深い地域であるため、ニシンは乾燥ものの身欠きニシンである。「ニシンのすし漬け」とも呼ばれる。
作り方
水洗いした身欠きニシンを桶に並べ、上に飯とサンショウ葉を置く。何層にもして桶が一杯になったら落とし蓋をして重石を置き、約ひと月間、発酵させる。 ハヤずしと同系の料理で、調理法にも共通点が多いが、このニシンずしの方が比較的多くの人に愛好されているのは、ニシンそのものが当地方において貴重な蛋白源として広く普及していたことことと、材料の魚があらかじめ加工されているために腹出しや塩締めなどの下処理が不要であったためであろう。
かどのすし漬け(岩手県)
名称の由来
カドはニシンのこと。「すし漬け」は発酵ずしのことで、この場合は改良型ナマナレに相当する。
特徴
東北地方の醗酵ずしは日本海側に顕著で、太平洋側では乏しい。岩手県においても発酵ずしの伝承はほとんど見られないのであるが、奥羽山中の湯田あたりは古くから秋田県との交易が盛んであった。その影響であろう。
「ハタハタのすし漬け」やカドのすし漬けがよく作られる。 ハタハタのすし漬けは正月料理であるが、カドのは春に作られる。たくさん作り置いて、田植えの時のおかずにしたものだった。
作り方
カドはぶつ切りにして、塩を混ぜた酢に二日ほど浸しておく。ご飯は糀を混ぜて、その後、やや塩辛いくらいに塩味をつける。桶にご飯をふり、カドを置き、上にご飯をまたかぶせる。これを繰り返してご飯の層とカドの層を積み重ね、最後にサンショウや笹の葉を置き、落し蓋と重石を置く。約10日で食べられる。
アユのくされずし(栃木県)
特徴
鬼怒川中流域および荒川や箒川(ほうきがわ)の最上流域で見られた習慣で、秋に漬けて食べる発酵ずし。近年では、上河内村・氏家町・塩谷町などごく一部で残る。約一週間の発酵をさせ、飯も食用とする点でナマナレの部類に属する。材料は発酵促進剤を用いない古い形態であるが、一方で、ダイコンも使う。イズシに代表されるように、野菜を混用する発酵ずしは糀などの発酵促進剤を併用するのが一般的であるが、この材料構成は非常にまれである。
また、魚を切り身にして飯に混ぜ込んでしまう。これも、イズシを除けば昨今の発酵ずしでは大変めずらしい。かっては一尾ずつ開いたものを飯の上に貼り付けており、切り身にするのは、ダム建設などでアユが遡上しなくなり、アユが入手しにくくなってから始めた策である。
作り方
材料のアユは7月ごろに捕り、一尾ぐるみ塩漬けにしておく。すしに漬けるのは、秋祭りの前で、塩出ししてから切り身にする。これを飯とせん切りダイコンとともに混ぜて桶に詰め、一週間ほど寝かせてから桶を逆さにし、水を切る。その後、桶から杓子ですくい出し、皿盛りにして食べる。
イワナずし(群馬県)
特徴
利根川上流域の三上町藤原地区に伝わる古習で、正月料理として作られる発酵ずし。魚と塩とご飯だけで構成される、古式ナマナレである。
作り方
イワナは3月から9月までが漁期で、この間に釣って、腹を出して塩処理をする。かっては塩漬けであったろうが、最近では腹側に塩を塗り、冷凍保存しておく。10月~11月ごろ、すし漬けにする。 固めに炊いたご飯を握り、表面にサッと塩をつけ、イワナの腹に詰める。桶にイワナを並べ、、一杯になったら落とし蓋をして、重石を置く。20日からひと月ほどで食用になる。ワサビ漬を塗って食べると、乙な味だ。
存亡の危機
だいたい発酵ずしの伝承が希薄な関東地方にあって、発酵促進剤も香辛野菜も使わない古式ナマナレハ極めてめずらしい。今や唯一と言っても過言ではない存在であるが、これも目下、存亡の危機に瀬している。
くさりずし(千葉県)
特徴
改良型ナマナレの典型例で、九十九里地方では日常食とするほか、正月料理として好まれる。材料は、アジやサバなどが使われることもあるが、中羽イワシのすしが真骨頂であろう。
作り方
イワシは背開きにして内臓を取り、よく水洗いする。これを塩に漬けて、一晩おく。きざみショウガを混ぜたすし飯を作り、イワシの腹に詰め込んですし桶にギッチリと並べる。一段並べ終わったら、せん切りショウガやユズ皮をふり、またイワシを並べてゆく。この時、ショウガをすりおろして、しぼり汁をかける人もある。最後にハランやユズの葉を敷き詰め、桶の内側の縁にワラの三つ網みをめぐらせて、落し蓋と重石を置く。2週間ほどで飯粒が溶け、食べごろとなる。
早ずし作り方
イワシは背開きにして内臓を取り、よく水洗いする。イワシを塩で締め、半日ほど酢に浸けたものを使うと2日ほどの発酵で食べられる。?ここに説明文が入ります。ここに説明文が入ります。
江戸前握りずし(東京都)
「江戸前握り」とは「江戸前ずし」と「握りずし」に分けて考える必要がある。
「江戸前」とは「江戸の前」すなわち江戸湾(東京湾)のこと。もとはウナギ屋の言葉で、江戸湾で水揚げされたウナギを「江戸前ウナギ」と言った。これに習い、「江戸前」で獲れた魚を使ったすしが「江戸前ずし」ということになる。幕末期、妙なことにウナギ屋では「江戸前」なる言葉が消えていったのに反して、すし業界では「江戸前ずし」という言葉が横行していった。
「握りずし」は、文字通り「握ったすし」である。室町期におけるナマナレの発生以来、すしとは、ご飯と魚とをいっしょに押し固めたものであった。その押しの工程を、箱・桶や重石の力を借りることなく、人の握力のみに委ねたのが、「握りずし」である。
握りずしの発明者は ちまたでは江戸は文化・文政期のすし商華屋与兵衛だとされる。その与兵衛の子孫にあたる小泉清三郎によれば、彼は、魚身を貼って握ったすし飯を笹の葉で仕切りながら箱に詰めて押すといった従来の方式を改め、箱で押すことなく自らの手で握り固める「握り早漬け」なる方法を編み出したという。
「江戸風の握りずし」 華屋与兵衛の時代以降、「握り早漬け」は世に好評を持って迎えられたことは事実である。まさに、江戸のすし商から生まれた形態で、江戸特有ともいうべきこの「握り早漬け」は、いつ、誰からともなく「江戸ずし」と呼ばれるようになる。この言葉が、「江戸前ずし」と習合したのであろう。「江戸前ずし」とは「江戸湾で獲れた材料で製するすし」というより、「江戸風の(江戸生まれ)握りずし」という意味の用語として定着した。
「江戸湾産の材料のすし」の意味 もちろん、握りずしが発生した当時は輸送技術も知れたもので、結果的「江戸前」のものばかりを使っていたことは容易に想像できる。けれども、握りずしが「江戸前」産以外の材料にまで手を広げたのは案外古く、明治期には外房や相模湾の魚介類も握っていた。それでも「江戸前ずし」だったのである。すしダネの産地にかかわらず、「江戸前ずし」と呼ぶことに抵抗がなかったのは、この言葉が流布するころにはすでに、「江戸湾産の材料のすし」という意味が薄れていたからに相違ない。握りずしの代名詞くらいに見ておいても差し支えないだろう。こんな事情であるから、何をもって「正当な江戸前ずし」とするかを規定することは難しい。
江戸の郷土料理 明治政府が東京の文化をもってスタンダードとしたことに始まり、関東大震災・東京空襲によるすし職人の流出と戦後の委託加工制度が追い風となって全国に広まり、今や、最も一般的なすしになっている。
現在と幕末・明治時代相違点
▲すしダネの下処理
現今は、いわゆる刺身をそのまますし飯に乗せることがごく普通になっているが、これはり氷冷蔵庫以後に起こり、電気冷蔵庫の普及とともに定着した風であって、保存技術の乏しかった時代にあっては、あり得ないことだった。生魚を準備して客を待つ商売では、当然、魚が損傷しないような処理を施すことになる。たとえば、塩で締める、酢で締める、ゆでる、焼く、ヅケ(醤油漬け)にする。などである。したがって、すしダネにはすべて調味が施してあるわけで、つけ醤油は不要であった。
▲握りの大きさ
明治初年の与兵衛ずしの握りずしで、それは現在の握りよりも2~3倍の大きさであった。あまりに大きすぎるので、後でこれを2つに切って供するようになった。これが「2カンづけ」の起源となった
▲お好み注文
すし屋のカウンターで職人と向かい合い、好みのすしダネを注文する方法も、当初はなかった。屋台では、あらかじめすしが握ってあり、客はそこから好みのものをつまみあげる。だからこそ、客は座るまでもなく、立ち食いで十分だった。ただ、この方法だと、売れ残りが出る可能性がある。そこで、客の注文を受けてから握るようになった。
▲文化的な意味
今日では、握りずしといえば高級料理というイメージがある。が、当初はとんでもない話で、屋台で気軽に食べるものであった。客は、小腹を満たすためにフラリと立ち寄り、たったままで3つ4つをつまんで帰る。
▲酒を供するは当然
今は「すしの味がわからなくなる」とて、酒を出したがらないすし屋も多い。けれども昔はそういう繊細なことは言わなかった。発酵ずしの時代からすしは酒の肴であって、酒を供するのは当然のことだった。けれども、屋台の商売ではそこまでの手がかけられないし、来る客はすでに呑んでいる場合が多い。よって酒を出ない店も多かったのである。
▲低廉な屋台店
どちらかと言えば、高級とはいえないのが握りずし屋台であった。出入りするは圧倒的に男性が多く、女子供は持ち帰りか出前で食べた。むろん、店舗を構える者もあったが、与兵衛ずしでさえ、最初は路地奥の2間しかない店であった(天保7年1836『江戸名物詩』)。その一方で、高級感を売り物にする すし屋もあった。
▲すしが高級料理に
文化年間に大阪から進出して深川で開業した「いさごずし」は、付近の名勝「安宅の松」にちなんで通称「松がずし」「松ずし」などと呼ばれた。この店の商売は派手で、しかも価格は常識を外れるものだった。当初は魚の姿ずしなどを売っていたようだが、握りずしができてからはこれも商うようになり、「卵は金、魚は水晶のごとく」というその高級感が世にもてはやされた。これに同調するすし屋も後を絶たず、これにより、すし屋は、屋台などの低廉なものと高級路線の乗ったものとの2系統に分かれた。高級な店は、天保の改革時に質素倹約令に触れて処罰されたが、以後また復活し、現在に至る。握りずしが高級料理になったのは、彼らの仕業である。
▲屋台店への規制
一方の屋台店は、衛生と交通安全の理由から、昭和初年までにその多くが規制された。結果、握りずしは高級料理としてしか存在しえなかったのである。
▲回転ずしが屋台店商法と共通
昭和40年代から、持ち帰りずしや回転ずしが流行し、いまや気軽な価格で食べられるようにもなっている。とりわけ回転ずしの人気は高い。「すし通」連中からはいろいろと揶揄(やゆ=からかわれる)されるが、よけいな作法をうるさく言わない、あらかじめ握ってある中から好きなものを選び取る、などの商法は、まさに江戸前握りずしが登場したころの屋台店商法と共通している。
笹巻き毛抜きずじ(東京都)
現在のすしダネ
すしダネを乗せた握りずしを笹の葉で巻いたもの。江戸末期には江戸での大変な人気商品であり、現在でもこのすしダネは、タイ・おぼろ・卵焼き・海苔・光り物・白身魚・エビの7種類となっており、光り物と白身魚は季節によって魚種が異なる。たとえば光り物は、春のサワラ、夏のアジ・サヨリ、冬のコハダといった具合。白身魚は、ワラサ・カンパチ・シラウオのほか、アワビや貝柱なども使う。
現在のすしの作り方
魚は塩で締めてから、強い酢で締める。その後、毛抜きを使って小骨をとり、あらためて今度はやや弱めに酢に浸す。 初出文献 「笹巻きずし」「毛抜きずし」野永文献にあがるのは1700年代の後半のことである。「笹巻きずし」は安永6年1777『土地万両』、「毛抜きずし」は天明7年1787『七十五日』もしくは『江戸町中喰物重宝記』が目下のところの初出文献である。
商品名の由来
天明のころ、「笹巻きずし」と「毛抜きずし」は、それぞれ別個の商品名であった。ただ、「けぬきずし」という商品を売っているのが江戸「へっついばし」の「笹や」なる店であったことから推測すると、あるいは笹で巻きつけてあったのかもしれない。「けぬき」はやはり「毛抜き」で、これを骨を抜いたことに由来していると思われが、『皇都午睡』(嘉永中期1850ごろ)には◆骨を抜く道具かと思いきや(毛抜きのように)よう食う という謎かけだったと、述べられている。これは、やや後づけの理屈に思われるが。
「笹屋」のけぬきずし
現行の毛抜きずしと同様に、魚身を貼ったすし飯を握り笹の葉で巻いたものだったかどうかは明言できぬが、それは、桶に詰めてしばらく押しをしておいたものだった(嘉永9年1849『守貞漫稿』)。
これは、いわゆる江戸前握りずしが成立する前段階と符合する。すなわち、今日的な握りずしになる前には、すし飯を握って魚身を貼りつけ、これを笹の葉で仕切りながら箱に詰めて押すというものがあった。箱と桶の違いはあるが、製法的には、まさにこれに相当するわけである。
笹ずし(新潟県)
長野県北部から新潟県中南部の山あいに伝わる。製法的には江戸末期の握りずしの原型の様相を呈するが、材料には生魚は使わず、質素の感がある。
笹の葉を皿に見立て、すし飯を握り、上に具を置いて笹に乗せる。ご飯は、餅米を少量混ぜておくと握りやすい。具は、ゼンマイ・シイタケ・オニグルミ・ダイコンの味噌漬けなどを細かく刻んで、一緒に炒りつけた後、煮詰めたものである。彩りに錦糸卵や紅生姜を添える人もある。サケのそぼろを乗せる家もあるが、概して昔は素朴な具しか乗せられず、魚を使うのは相当に裕福な家であった。すしの乗った笹を押し箱の中に丁寧に並べ、何段も重ねてから蓋をして、軽く重石を乗せて味をなじませる。
こうした製法のほかに、一般的な箱ずしのように、箱にすし飯を詰め、具を貼り、葉で仕切り・・・、という作り方もあるようだが、今日、この地方の笹ずしといえば、ひとつひとつを笹に盛るものが良く知られている。最近、長野県飯山市富倉地区では、全国発送の販売法も確立した。
越後ではこれを「わらじずし」とも呼ぶ。細長く扁平に固めたご飯を、わらじに見立てたのであろう。また、信濃側では「謙信ずし」とも言うのは、一説に、このあたりを治めた越後の戦国大名上杉謙信が兵糧としてこのすしを用いたとも、村人たちが出陣する上杉勢に献上した(よって、このすしは越後の春日山城と信濃の川中島を結ぶ道筋に残っている)とも伝えられるからであるが、戦国時代には酢を使うすしの存在はかなり微妙であるし、あったとしても、それは生魚の発酵食品から派生したものであるため、精進物ばかりのすしではなかったはずである。