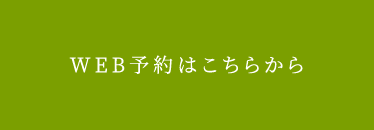鮨を知る
 UOTAKE SUSHI
UOTAKE SUSHI
江戸前鮨

2021年9月19日
江戸の食文化の革命は屋台店から
行商・辻売り
1、武士は伝統的な食事を厳守
江戸時代は、近くて遠い。庶民たちの生活を律していた。様々な風俗習慣は現代人の記憶の彼方へ追いやられ、単なる俗信として忘れ去られている現状にある。当時の人々は月ごとの行事を遵守し、四季に行なう年中行事に従い、それに合わせて食文化を維持してきたのである。
当時の身分の高い武士階級や裕福な商家の人たちは、決して外食をしなかった。外出の際には弁当を持参し、あまり長くない外出では帰宅してから昼食を摂るのが通例である。
食い物屋に入って物を食べたり、行商人から食物を購入したりすることは、下賎の者が行なうことであると信じきっていたのである。特に女性は一生、外食などは無縁であった。
江戸の為政者たちは、何よりも秩序を重んじ、その秩序を破壊する虞があるものは徹底的に阻止した。それは、頭が固く嗜好の限界がそこにあるのではなく、幕府の政治が作り上げた秩序の保全だけに力を注いだことによる。
江戸の中期までは食べ物を扱う店は、町中にはほとんど無いというのが現状であった。よく、映画やテレビの時代劇で、両刀を差した武士が居酒屋などに入って酒などを飲むシーンがよく見られるが、あれは江戸の現実では有り得ない。浪人の武士でも、外食などをすれば「何と、下賎な!」とさげすまれるのがオチで、武士の対面に係わる問題である。
時代考証をしっかりしてもらいたいと願うが、江戸の末期にならなければ居酒屋は登場しないし、そこで安酒を食らっているのは馬子か陸尺か日雇いなどの力仕事に従事する輩ばかりで、武士は決して寄りつかんなかったはずである。
このように、食習慣を墨守している階級からは、新奇な食文化の発展は望むべもない。食の冒険者は、その日暮らしの庶民たちなのであった。
2、当時の売食産業は零細な「ボテ振り」
経済的にもギリギリで、その日その日を暮らしている。長屋住まいの庶民達は、安価で滋養のある食品を求めていた。その需要に応じたのは「ボテ振り」と俗称された行商である。町々を経巡り、長屋の中まで入り込んで、庶民の生活の必需品を、天秤棒で担って売り歩いた。
「俳句」 ◆先々の時計となって小商い
毎日、同じ時刻に々町並みに来る行商もあり、住人からは「ああ、豆腐売りが来たから、六つ半だな」などと、時計の代わりになるのである。庶民たちの日常生活とこれらの行商との関係は、かくも密接であり、生活に深くかかわっていたのである。
庶民の生活で、いちばんの必需品は「灯し油」「薪・炭」などの燃料と、主食である「米」である。これらも毎日、行商から購入するが、前日の収入に応じて、「灯し魚油」一合「炭」は十匁「米」は三合などと、少量ずつかうことが多かった。
食料品でもいつも人気の高いのは、鰯である。生で買う場合もあり、目刺の干物として買う場合もあるが安価で旨いので毎日の飯の菜としている。 行商者も零細な庶民であるが、よく売れる商品を常に開拓し担い歩いたので、文化・文政期にはそれをさかのぼること50年前には想像も出来なかったほどの食品が売りさばかれた。深窓にいる人々が旧態依然として、伝統的な食べ物を食べ、珍奇な食品は下賎であると排斥する中で、一般の庶民達は、まぐろ、ふぐ、うなぎ、スッポンなど食べ始め、スイカ、カボチャ、トウモロコシなどが美味であると分かると、それらの新しい食品はたちどころに庶民の食卓を賑わしていったのである。
3、「下馬先」で食べる安価滋養食品
また、武家屋敷の一隅の長屋にいた下層の武士たちは、仲間・駕篭かき・槍持ち・奴などであるが、これらの人々も武士のはしくれであるが、生活意識は庶民となんら変わる所がない。生活が困窮していたから,安くて旨いものを買い求め、また内職にも精を出さざるを得なかった。殿様が公式な用件で外出すれば、行列に付き添い、殿様が江戸城にでも参内すると「下馬先」でじっとたむろしながら待っていなければならない。 冬季には、寒さに打ち震えながら、ただひたすら控えているだけである。手持ち無沙汰で何もすることは無いが、立ち去る事は出来ない。そこに出現したのが、「辻売り」屋または「下馬売り」である。初めは、冬には温かい茶を商い、夏には冷やした麦茶などを商った。あまり派手に商売をしたのでは、いつお咎めがあるかわからにので、目立たぬように売り捌いたが、次第に軽食を扱うようになる。安価で腹のたしになるものと言えば、これまで食用として見向きもされない食品の開発につながる。 買い食いするほうでも、何を売っているかわからない代物ばかりであるので、仲間たちは、「これは何だい?」と聞きながら確かめて買う。焼き魚であれば、下魚として見向きもされない秋刀魚であったり、醤油の煮汁の中に入れた「つみれ」や「茹卵」であったり、小魚を串に挿して油で揚げたものであったり、小さな握り飯に安魚のみを張りつけたものであったり、ともかく普通では食べないないような珍奇な物が扱われた。火を使うことは、「下馬先」では禁じられていたから、商人はあらかじめ調理した食品を取り扱った。ちなみに、「醤油の煮汁の中に入れたつみれや茹卵」は「おでん」であり、「小魚を串に挿して油で揚げたもの」は天婦羅であり、「小さな握り飯に安魚のみを張りつけたもの」とは「鮨」なのである。 旬に「入れ上げる」とあるから、皆争って買い求め金銭を使い果すほどの、熱中振りであることがわかる。これを食べた人々は、「こりゃ、旨いもんだ。家にもって帰って、かかあや餓鬼にも食べさせよう」という思いを抱き、家ぶとにする。庶民たちは、いちはやく時代の先端を行くそれらの食料を食べ、その旨さが喧伝され、それらの珍奇な食品はじわじわと一般に浸透して行くのである。食の文化の冒険者たちは、これらの庶民なのであった。
4、稲荷鮓は油揚げにおからを詰めたもの
江戸の末期から庶民に馴染みの深い稲荷鮓は、現在のとは違い、油揚げに豆腐のおからを詰めた安値で滋養に富む食べ物であった。天保7年の大飢餓の頃、その安直さと低廉さで流行したとされる売価は一個四文。「さへづり草」(天保~文久3-1833頃~1863)には、「去年(弘化2-1845)より江戸のちまたを、夜となく昼となく歩行くいやしき食類に、稲荷鮓といへるものあり。(略)稲荷鮓はいかなる物と聞きけるに、豆腐の油揚に雪花菜(きらず)を包めるものの由、かくしてこれを稲荷鮓と命ぜしぞ」とある。
「藤岡屋日記」にも、弘化2年10月頃から流行とあり、天保期に引き続いて第2の流行期を迎えた。日本橋の十軒店辺には、「次郎公」と愛称された名物の売り手もいて、多くの稲荷鮓の行商者がいずれも元祖と名乗っていたという。
低廉で素早い、江戸前の握り鮨
1、鮨のはじめは「なれ鮨」 鮨は『土佐日記』(934頃)にも記述されているように、平安時代以前から、食品として存在している 。この鮨は「なれ鮨」である。鮒・鮎・鯖などを用いて、はこ・桶に飯を詰めその上に魚を開いて乗せ、重しをかけて魚のエキスが全体にしみ通るまで馴らすのである。大津の駅弁で、今でも名物の「鮒鮨」としてはんばいしているが、古来の姿を残しているものとして、興味深い。しかし、魚の匂いを好まない人々にとっては、生臭くて食べられる代物では無いという。『江府風俗志』(寛保~延享1745年頃)には、 この頃の鮨は「なれ鮨」である。鮎・鯖に限りて飯に漬け置きて、日数を貯えて、酸くなくなりし物を鮨として 賞翫 (しょうがん)(味のよさを楽しむこと)したるなり。 とあり、江戸の中期まではすべて「古鮨」(なれ鮨)であった。 粋な扮装に頬被りした若者によって、鮨の行商が行なわれた。「鯵のスー、こはだのスー」と呼び声を上げながら、特に吉原などの遊里に出入りした鮨売りは、はこを何枚も肩に担いで巡り歩いた。 売価は「一筥(はこ)十二に軌って四文に売る」とあるので、一個なら四文、一筥ならば四十八文ぐらいである。低廉な蕎麦が一杯十六文から二十文と考えれば、「なれ鮨」の大体の目安がつく。
洒落本『青桜松之裡』(享和2-1802)には、 口を酸くして呼ぶ、鮨売りの声は、おしつよき客のこごとかと疑うばかり。 とあり、夕闇がしだいに迫って来る頃、吉原遊郭内の道々を鮨売りは、「ぞめき客」(登楼する当てはないが、何となく廊内をそぞろ歩きしている男たち)の間を縫うようにして売り歩く。
◆鯵のすふこはだのすふと賑やかさ
鮨売りの声を活写した句である。
2、鮨の第一の転換はコハダ・アジの「当座鮨」 『後はむかしの物語』(享和3-1803)には、 おまん鮓は宝暦の頃よりと覚ゆ。(略)此ころまでも当座鮓を売事は稀也。鮓売といふは丸き桶の薄きに古き傘の紙を蓋にしていくつも重ねて、コノシロの鮓、鯛の鮓として売りきしは、数日漬たる古鮓なり。
とあって、「古鮓」に代わって「当座鮓」が宝暦の頃(1751頃)から出回り始めた。これが鮨の第一の転換期である。 「当座鮓」は早鮨ともよばれ、桶で馴らすことをせずに、飯と具を桶に入れてちょっと押さえ漬けるようにして、そのまま食べるもので、簡便さを狙った鮨である。その手順は「浪華百事談」(明治25~28頃〕巻の6に記載されている。
鮓とよべるものは総てすし桶に製して、早くも一日一夜、ある日は二日も経て後食用とす。然るに酢箱に飯を入れ、魚肉精物をおき圧板をおき、両手にてよくおして直ちに売るものをかくいひ。また暫時重石をおきて売るも、また早ずしと云ひしとぞ。
この頃鮨のタネは、コハダ、アジが主であった。
◆けちな鮨コハダの皮に飯を張り コハダの魚肉が透き通ぐらい薄くて、それが飯に張りつけてある状況である。
この句は寛政11年〔1799〕刊行の柳多留に掲載されているので、まだ握り鮨ではなく、早鮨である。この早鮨が簡便であり、また売れ行きも良好なのを受けて、いよいよ握り鮨が登場することになる。
3、握り鮨は文政年間(1800年代初頭)に屋台店から 人々がい渭集する隅田川河畔などの盛り場で、屋台店が発祥である。低廉で、素早く食べられるのが特徴であった。
◆妖術といふ身で握る鮨の飯
「妖術という身で」というのは、妖術遣いが印形を結ぶ手付きを連想させる身振りを言う。これは、左手の掌に右手の二本指を当てて握る印形である。飯を左手の掌に置き、右手の二本指でその飯を押さえながら握る動作で、現代の握り鮨の法とまったく同じである。「柳多留」百八篇は文政12年(1829)の刊行であるので、この頃に江戸前の握り鮨が出始めたと推測できる。鮨の握り方が珍奇な動作として庶民の目に写ったのである。
◆握られて出来て食い付く鮨の飯
屋台の鮨屋で、簡便に作られ、それを食べている状況である。「柳多留」百十三編は、天保2年(1831)に刊行されている。したがって、江戸の年号で言えば、文政年間、西暦で言うと1820の後半頃、江戸の握り鮨が出回り始めたと言える。
江戸前というのは
江戸湾で取れた生きの良いタネという意味ばかりではなく、すぐ近くの海から取れた安価のタネという意味合いが強い。
『江戸自慢』(江戸末期)には、鮨は握りて押したるは一切なし。調味よし。上方の及ぶ所にあらず。価もやすし。 と記され、四文銭の流通を考えると、一個四文で売り始められたと思われる。
その証拠となる資料は、十返舎一九の滑稽本『金儲花盛場』(文政13年ー1830)である。 「名物 寿し」「千秋万歳」と書いた箱看板を掲げた屋台の鮨屋が描かれ、そのうたがき詞書きに、次のようにある。
◆鮓見世 評判はよしののさくら鯛すしの されば買人もおしかけてくる と、短歌が添えられ、「じゃのすしもござります。そのほかおのぞみなら、てんぢくりうさ川のこいのこぶま き、 ずんごうのすずきのはやずし、にんぎょのすし、ちくらのおきののりずしも、おこのみならさしあげませう」
「わしはそんなむづかしいすしはいらないから、四文づつのを二もんにまけて下さい」 「さつまいものすしはないかへ。大ふくもちのすしならなほよかろう」
屋台の奥には握り職人が一人居て、屋台の前には四角な岡持ちを手に下げた丁稚が鮨を買う風情で立っている。タネとしては買い手てのお好みに合わせて、なんでも応ずることが分かる。
「じゃのすし」は「蛇の鮨」であり、「てんぢくりうさ川のこいのこぶまき」とは「天竺の流砂川の鯉の昆布巻」のことであり、「ずんごうのすずきのはやずし」とは、中国の「松江の鱸の早鮨」であり、「にんぎょうのすし」は「人魚の鮨」、「ちくらのおきののりずし」は千葉県の千倉沖の「海苔鮨」のことで、いずれも実現不可能なものを列挙している。要するに「お好み次第で何でも鮨にします。
ということの誇張表現である。
丁稚の台詞に「わしはそんな難しい鮨は要らないから、四文ずつのを二文にまけて下さい」とあるので、握り鮨の一個の定値段が四文であることが了解される。握り鮨が出始めた頃のネタは、コハダ・鯵・蛸などの「押す鮨」と同じようなものであったろうが、次第に工夫が凝らされ、人々の嗜好の現実を確認しながら、タネのバリエーションも広がっていった。
天保中期の様子は、『守貞漫稿』(嘉永6-1853刊)にある。 筥鮨の廃せしは五六十年以来漸くに廃すとなり。握りの飯の上に、鶏卵やき・アワビ・まぐろさしみ・海老のそぼろ・小鯛・白魚・蛸などを専とす。皆、各一種を握り飯上に置く。鮨には梅酢漬の生姜一種を添える。赤き故に紅生姜とも言ふ。刺身及びこはだ等には、飯の上、肉の下に山葵を入れる。
「ガリ」を添えることや、山葵を飯とタネの間に入れることや、ほとんど現代の握り鮨と同じである。
簡便で旨く、しかも低廉で早く食べられるので、この握り鮨は江戸庶民の嗜好に適い、いち早く江戸の町に広がり、屋台から鮨専門の店売りになり、江戸の末期には一町に鮨屋が23件も出来るという盛況になるのである。
江戸前という言葉を最初に使ったのはうなぎ屋
1. 徳川家康は江戸の街づくりに取り組み、石神井川の流れを付替えた。 江戸城の前の浅い海を埋め立てて土地を造成した。現在の宮城前、
馬場先門の辺りが沼に変わった。 その後この沼でたくさんのうなぎが取れるようになった。 人夫たち(大工工事)は昼飯の惣菜にと、このうなぎに目をつけた頭
の良い人物がいて、うなぎに味噌をつけてブツ切りにして竹串にさし、焼いて売り大儲けした。江戸(城)前のうなぎの蒲焼の誕生である。 そのうちに、「江戸前」の呼称は江戸の前の海で捕れる魚介類の呼称となった。
2. およそ文化年間(1818~1830)に、江戸で誰かが思いついたものらしい。それまで、すしは江戸でももっぱら関西流の押しずしだったのである。屋台の店のすし職人の誰かが、思いついてすし飯に刺身をのせ、握って、インスタントのすしをつくったのではないか、と思われる。 すでに箱ずしも押してその場でただちに食べられる早ずじが大阪で人気を得ていたのだから、押しずしを切り分けたひと切れのすしがヒントになったのだろう。 押しずしは本当は押してから少し時間がたった方が、具とすし飯が調和して旨い。しかし気の短い江戸っ子には、悠長な食べ物は気に入らなかったとみえ、目の前で握って即座に食べられる握りずしがあらわれると、たちまち爆発的な人気をとったらしい。
握りずしの時代
1. 江戸時代の後期、さまざまな形態のすしが生まれるなか、その最後を飾るかたちで、にぎりずしが誕生した。ときは文政、場所は江戸市中である。 時代は地方農村が荒廃する頃で、職を求める人々が集まってくる江戸は,とりわけ男性人口、が増えた。そうした事情と貨幣経済の発展により、かせいだ日銭が外食するという習慣が定着する。 江戸の街では、低廉な飲食産業や外食産業,一膳飯屋や屋台の食い物売りが軒を連ねるにいたった。すし商もその例外ではない。 やがて、一部のすし屋のなかには、高級化路線を歩み、世にいう天保の改革の奢侈禁止令に触れて罰せられる者まで出てきた。 そんなかで、握りずしが世に登場する。考案者は特定されないが、歩き売りから商売をはじめて超高級店にまで成り上がったすし商・花屋与兵衛の改良により、江戸中の評判になったという。 当初から商品としての位置づけが濃厚で、高級店はもちろん、場末の屋台でも売られるようになる。「外で食べるもの」「買って食べるもの」として世の人々に受容され、そのイメージが今もって存続していることは周知の事実であろう。
2. 握りずしは,いわば「江戸の郷土料理」であった。東京の握りずしが他の郷土のすしよりも一歩抜きん出る素地があった。また、大正12(1923)年の関東大震災では、罹災したすし職人がこれを機に故郷へ戻るなどして、握りずしの技術が各地に伝えられたという。さらに太平洋戦争では、戦災を避けて、あるいは焼け出されて、東京を離れた人は数知れない。
彼らもまた東京の情報を地方に伝え、このことが握りずしの普及に一役買ったことは容易に知れる。悲惨な歴史も、握りずしには追い風となったのである。
握りずしの誕生
江戸の食べ物の代表のように言われている握りずしであるが,いったい,この握りずしの起源はいつごろなのであろうか。きわめて庶民的な食べ物に,確たる記録があろうはずがないから,やむえない。そのいくつかを紹介してみよう。
第一の説
延宝年間(1672~1681)に会津天満宮の神官であった者が、江戸に出て松本善甫(まつもとよしいち)と名を変えて医者になった。この医者が,どういうわけか,すしを考案した。当時のすしは、昔風の熟れずしであったからその熟成(でき上がり)に日時を要したため、松本善甫が改良考案した。このすしは、待つ間もなく買うことができるものであったから,世間はこのすしを「待ちゃれず」また「早ずし」とも呼んで、有名になった。
これが江戸握りずしの始まりであるという説である。善甫が医者だけに、食酢をうまく使ってすしの熟成期間を早めたのではあるまいかとも考えられるが、いずれにしても資料が消滅したことは、なんとしても残念である。
第二の説
「文化のはじめ頃、深川六軒ぼりに、松がすし出来て、世上すしの風一変し・・・・」とあることによっ て、「松がすし」が握りずしを創案したので世間のすしの有様が一変した、とする説である。
この店の店主は堺屋松五郎といってることからすると、松五郎は上方人で泉州堺の出身者ではないかと考える。彼は当時の関西風箱鮓を基本として鮓を引っ下げて江戸へ出店したのではなかろうか。「江戸安宅の松が鮓の精製(中略)・・・・・この家の海苔ずしは、飯と魚と海苔と、渦巻に作る也。
外のは、海苔を衣に巻くのみ也。この松五郎は、鮓を売り出しし始、所々の控所に行き、わが手製の鮓也とて遣わし、(中略)・・・・心つけ給えといいしとぞ。鮓の中に壱朱銀などを入れおきしなり。・・・・」とある。すし飯の中に壱朱銀を入れる話には驚かせる。松五郎の商策は大当たりで、店はますます繁盛の一途をたどり、そのすしもしだいに高級化し、値段も天井知らずの思い切った高さだったという。
というわけで、松五郎の優れた商才はよくわかるし、その超繁盛ぶりがすし業界に与えた大きな影響も想像がつくのだが、かんじんの握りずしの創案者かどうかは、明らかでない。
しかし、「松が鮓」は、「與兵衛」、「毛抜き鮓」と並んで江戸の三大すし屋と評判をとり、明治の末まで続いた名店であった。
第三の説
「初代花屋與兵衛」が握りずしの創案者であるという説である。 この與兵衛(1799~1858)は、福井藩出入りの八百屋のせがれで、九歳の時に、江戸・蔵前の札差板倉屋清兵衛方に下男奉公に入り、十数年間を勤め上げる。父は泉籐兵衛、という。福井藩の下級武士ではなかったかと考えられる。彼は二十数歳で板倉屋を退いた。がんらい器用な性質だったらしく、握りずしを創案したと伝えられる。文政(1818~1830)本所横綱(現在の東京都江東区)の長屋に住んでいた。 毎夜、我が家に近い岡場所(私娼窟)を夜明け頃まですしを売り歩いて小金を貯め、尾上町(両国回向院前)に小さな店を持って,『與兵衛ずし』の看板を上げた。この店が当たりに当たって江戸中の評判となり『松がずし』と同じく武家屋敷からの注文も多く、こみあいて、待ちくたびれる與兵衛鮓 客もろ手を握りたれけり という狂歌があるくらいで、與兵衛の努力は報われたのである。文化(1804~18)の終わりに近い頃であった。
その他握りずし誕生説
イ、すしは政治的贈答品中の雄なるものであったから、数多い注文にすし屋各店がその技術を競っているなかで創り出されたのが握りずしであろうと元東洋大学教授の増田義一郎先生が『嗜好』で述べられている説である。
ロ、これもさしたる根拠などないようなものだが、『柳多留』文政10年(1827)3月26日開の句に「妖術とい身でにぎるすしの飯」というのがある。つまり、ドロンドロンと妖術使いが印を結ぶときの様子が、すしを握る手つきに似ているというところからきている川柳である。握りずしに関する句としては,一番古く,他にこれという資料も見当たらない今日,握りずし出現の時を文
花屋與兵衛とは 『與兵衛ずし』店は、昭和の初期まで同じ場所で営業していた。この店がまさにすし業界における文字通り老舗であったことは間違いないのである。ただし、初代與兵衛をもって江戸握りずしの創案者とすることはいかがであろうか。創案者でなく、大成者とするほうが当たっているのではないかと思う。 與兵衛に関する記録類が残っていそうなものであるが、日本米食史などに引用されている『またぬ青葉』(與兵衛の親戚筋に当たる浅草の浅倉屋書店主人が明治初期の写本)も、同じ主人著の『鮨考』も残念ながら関東大震災で焼けてしまった。従って與兵衛に関する記録類はないとのことである。
江戸のすし屋が握りずしに転向
握りずしが大流行
『松がずし』や『與兵衛ずし』の繁盛に影響されて、江戸のすし屋のすべてが握りずしに転向したようである。 『守貞謾稿』は、天保(1830~44)末頃のすしの様子と値段を次のように記録している。
箱押しずし(方四寸)48文。コケラずし(鶏卵焼、あわび.鯛等)64文。 毛ぬきずし(握りずしを熊笹に巻く)1個6文也。
江戸今製の握りずしの価格
鶏卵焼、車海老、海老ソボロ、白魚、マグロサシミ、コハダ、アナゴ甘煮長のまま。以上の価格8文鮓也、玉子巻は16文ばかり也。 他に、貴価のもの多く、鮓、1ツ4文より、5,60文に至る。天保府命(有明な天保の改革老中水野越前守忠邦が天保12年(1841)に発した政治改革で極端な奢侈(しゃし)禁令が行なわれた)の時貴価の鮓を売る者200人余人を捕まえ、手鎖にする。その後皆、4文、8文のみ、府命、ゆるみて、近年2,30文の鮓を製するものあり・・・・ 散らし、五目鮓に椎茸、きくらげ、玉子焼、紫のり、めじそ、蓮根、筍、鮑、海老、の魚肉は生を酢に漬けたる等、皆、細かく刻み、飯に交え、丼鉢にいれ、表に金絲玉子焼きなどを置きたり、丼と云うは、一人分を小丼鉢にいれて、価、100文或いは150文也・・・・と記している。 当時、ウナ丼が1個100文から200文、どじょう汁、鯨汁1椀が16文どじょう鍋は48文である。
松浦静山(1760~1841)の『甲子夜話』には、「近頃、大川の東、安宅に、松鮓と呼ぶ新製あり。松とは売る人の名なり。これよい味、一時、最賞用す。この鮓の価、ことに貴く、その量、五寸の器、二重に盛て、小判三両(現在の価格に換算は約24万円)に換えるとぞ。これを制するもの、鮓、成て、これを試食し、その味、意に適はざれば、即ち、棄てて顧みずと云う。この如く貴価の品、今に行はるるも、また世風を観るべし」とある。 松すし(松がずし・堺屋松五郎)の勢いのよさ、あるいは思い上がりぶりがよく分かる。十両盗めば首のとぶ世の中で、三両のすしがよく売れたものである。 ともあれ、握りずし誕生の頃、江戸にはグルメの時代があったのだ。
江戸の屋台店の繁盛
『守貞謾稿』の嘉永 前後の記に、屋台のすし屋のスケッチと説明がある。 「下図の如き見世及び台のみにて屋根無きをも京坂にてはこれまた出し見世と云う。
江戸にてはヤタイミセ(屋台店)と云ってはなはだ多し・・・・屋体見世(屋台店)据え、店にて不用の時は他に移す ・・・・このうらに横木ありて他に移すにはここに拐(げ)を掛けになひ運ぶ京坂にはこれ以上を造らず是より以下の如き台しかの店多くまた図の如く屋根あるもの往々有し・・・・ここに障子あるははなはだまれなり・・・・屋体見世は鮓 天婦羅をもっぱらとす其の他皆食物の店のみなり あら酒肴(さかな)を売るもあり 菓子あん餅等にもあるとも鮓と天婦羅の屋体見世 夜行繁きところには毎町各34ケあり 天婦羅は自宅にて売るにも必ず宅前にこれ置く 鮓店には或いはこれ置く或いは置かず ・・・・老店及び名ある店」そして、店名は御膳寿し間口は6尺、奥行きは3尺とも書き入れてある。
他の個所には「江戸は鮓店はなはだ多く毎町12戸 蕎麦屋12町に1戸あり酢屋名あるは屋体見世を置かず 普通の見世はもっぱらこれを置かず 又ヤタイミセのみて売るも多し」とある。
江戸時代末期の江戸のすし屋の状況を最も詳細に伝えてくれた貴重な記録である。 そのすしは、おそらく殆んどが流行の握りずしだったろう。たんじょうして4、50年の間に、そばやうどんをはるかにしのぐ人気の食べ物となったのだ。
その握りずしを商うすし屋の様子も詳細に捉えられている。名のある店は屋台を置かず、普通の店はもっぱら屋台を置いているし、屋台だけで売るすし屋も多い、というのである。名のある店とは、おそらく、『松ヵすし』や『與兵衛ずし』のような高名な格式のある店のことだと思われる。料亭のような立派な構えのそうした店は、座敷ですしを供したのだろうし、屋台など置くはずがない。
普通の店といっているのが『内店』と呼ばれる店で、大正時代初期までそうであったように、もっぱら顧客のあらかじめの注文を受けてすしを握り出前してお届けするという商法で、店で客に食べさせることはしなかった
昔の屋台のすし屋は出店の場所が一定していた。組み立て式の店を、担ぎ棒で二人でかついで決まった場所へ運んだのである。担いで行くのだから、屋台のすし屋は自分の家からあまり離れた場所には出なかった。自分の住む町内の横町の角や、路地の入り口、それに銭湯の近くで、夜早く店を閉める家の軒先を借りるなどして出店したのである。
下町に屋台のすし屋が多かったのは、同じ町内の住人が顧客のわけであり、殆んどが顔見知りだから、いい加減なすしを売るわけにはいかず、また同業の屋台店との競争もあり、すし職人の職人気質も手伝って、お互いに腕を競ったものである。屋台店での商売は小資本で始めることが可能だったから、屋台ずしは若いすし調理師にとっては登竜門だったともいえるのである。
江戸の町での屋台ずしの隆盛は、出前販売専門だった内店に影響を与えないわけがなかった。
明治以降のすし屋
屋台店が内店に影響
太平洋戦争が始まる直前、東京市内のすし屋は3,100店前後、そして屋台ずし店が約800店あったという。屋台ずしの繁盛ぶりがうかがえる。 明治末期から大正時代にかけて現実に存在していたのは、普通の店と称する内店の入口に向かって右側か左側に取り付けられた付属屋台である。
「名ある鮓は江戸時代末期には屋台店を置かず・・・・」とあるようにプライドが高かった。しかし、時代が下ってくると與兵衛ずしでも、あらかじめ注文を受けていた出前をすませて夕方から付属屋台を開けて商売をした。
屋台鮓を区別すると、ニ種あって、一つは普通の店があり夜に入ると子息、なり老人なりが、小遣いとりのために屋台を開店する者ありました。すし種は煮物等、総ててが店売りと変わらない。
もう一つは薄資のために店を堂々と張ることの出来ないものが、日暮れを合図に、屋台を引き出して営業するのとあります。 薄資の屋台店はすし種は、海苔、まぐろ、赤貝、鳥貝、アジ、コハダ、たこ等位で、少し上等で、アナゴやハマグリも使ったが、海老、鯛の贅は殆んどなかった。
屋台店の職人はかえって腕のいい者が多かったし、また屋台での商売が若い職人の修行の場であった。 資本蓄積の心構えの乏しい江戸っ子の伝統を継いでいて、その日暮らしの、向上心のない職人の多かった事も事実であり、すし種も安価な物を使ったし、客の前で注文に応じて素早く握る必要から、ぞんざいなしごとになってしまいがちであった。
内店には、屋台店を初めは店の前から少し離れた場所に夜になると開店していたが、やがて本店とドッキングさせて常設の『付属屋台』とし、ついにはこれを店内に取り込んでしまった店もあった。
内店のすしと屋台店のすし店
舗を構えた内店では、漬け場と称する板の間に畳半帖を敷きそれに座って握った。すしは座って握るのが当たり前だった。座ったほうがきれいな仕事が出来た。 その習慣が屋台ずしにもそのまま踏襲されていたのである。昭和のはじめごろまで、内店ではこの座り仕事が普通だったようです。 内店は、高級な店は料亭式に座敷で食べさせ、普通の内店は出前と土産用にすしを握った。その場で食べるすしは、夜の屋台店が売っていたのである。 今と違って昔の握りずしはずっと大きく、到底ひと口では食べられず、ひと口半ないしふた口でやっとという大きさであった。だから、一貫ずつ握って供するのが当然で、屋台店の客は銭湯からの帰り道にちょとニ~三個つまむ、という食べ方していたのである。 独立の屋台店の握り手は、何しろ忙しい思いをしなければならなかった。五人も客が並べば満席である。次々に注文のすしを握らなければならないし、お茶もだす。勘定をして支払いを受ける、という仕事もある。それを一人でこなすのだから、忙しさは想像がつく。 お茶の湯のみが大きのは、何度も入れ換えなくてすむようにという理由からであったお茶を注ぐ手間さえ省かなければならなかったのだから、まして、酒など供している暇はなかった。 そこで手のこんだ調理はしだいに敬遠されることになりタネの魚や貝も加工に手間をかけるより生のままのほうが楽だし、仕事が早い。どうしても純生のタネに頼るようになる。
氷令蔵庫の出現
明治三十年代ともなると、氷冷蔵庫の出現によって生物の長時間保存がが可能となってきたから、生物オンリーに拍車がかかり、昔風のすしの影が薄くなっていくともに、すし本来の保存食的性格は次第に忘れてしまって来たのである。
押しずしの悠長さに対抗して、早漬け、つまり即製を目的に考案されたのが握りずじであったのだから、それがやがて即食主義にまで到着したのは、むしろ当然のことだったともいえるだろう。
だが、即製即食主義のいきすぎは、すし本来の保存食としての伝統を忘れさせてしまうばかりでなく、技術的にも、飯とタネとの味覚上の調和、つまり、すしの本来の「熟れた味」を第二義的なものとしてしまいおそれもあるのだ。
調理方法しだいで、折り詰めなどにし時間がたってもかえって「熟れた味」に独特のうまみがでてくるのがすしなのであって、けっして即製即食のみが握りずしの食べ方の総てではない。
時間がたてば自信のあるすしの味が落ちるから折り詰めのすしを売らないというのは、確かに心意気のようなものがあるが、これをもって東京のすし屋のお手本だなどと思われては、困る。
ただ生きている魚をタネにするというだけのために、いけすで生かしておいて客の前で調理してすしに握って自慢してみたりするようなことは、粗製乱造に陥りやすい。
「松がすし」は明治末年に、「與兵衛ずし」は昭和七年に店を閉じた。