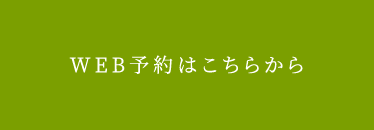鮨を知る
 UOTAKE SUSHI
UOTAKE SUSHI
江戸時代の俳諧・狂歌・笑歌

2021年10月1日
江戸の握り鮨を詠んだ最初の句
自来也(じらいや)又は児雷也は江戸時代後期、芝居小屋(浄瑠璃、歌舞伎)で蝦蟇の妖術(ガマのようじゅつ)を使って大活躍する盗賊忍者で大人気の物語です。
江戸時代は珍しい物を句にするのは、川柳の独断場である。
◆妖術といふ身で握る鮨の飯
これは江戸の握り鮨を詠んだ最初の句である。当時は芝居小屋が立ち並ぶ江戸有数の繁華街である両国、しかも勧進相撲興行の会場でもあった両国回向院前に文政年間(1818~1830)に小さな店『與兵衛』は握りずしの店を開いた。
芝居に登場する蝦蟇の妖術使い自来也が左手の掌(手のひら)に右手の指を二本包み込んで握り、呪文を唱える印形と、江戸前握りずしの開祖「與兵衛」がシャリを左手の掌に握り、その上にタネを乗せて、右手二本で抑えるように握る形状の類似性を目新しく、珍奇さを句にしたのである。
織田信長が皇居造営
滋賀県から人夫を多数集めて石をはこばせたおり、 京童は、
◆生成のすしにも似たる近江衆 石を重しと持たぬ日はなし
と一首ものした。この歌は同時に当時の京童が、すしといえば生成を連想 したことをも暗示する。
笑話集「醍睡笑」(寛永5年1628)
京都誓願寺の安楽庵策伝が所司代板倉重宗のために編んだ笑話集「醍睡笑」はすしの説話も数々集録されており、当時のすしの面影がわかって面白い。たとえば
◆破戒坊主がアユずしを剃刀となつけてひそかにたしなんでいた話。
◆小僧がすしづめになって寝ているのを老僧がひやかしたら「このように腹に 飯の入ってないすしは知らぬ」と答えた話。
◆川を徒渉して、泳ぐ魚をアユかと問うたら「アユにしては飯つぶが付いてない」 と答えた話。
◆僧と相撲として敗けた男が「こんなにすし臭い坊主は初めてだ」といった話。
◆雷のすしを食べたら「雲臭かった」という話 すしが京の町ではアユが主流であり、それが生成で腹に飯が詰め込んであった。 また僧院でも内密にすしが漬けられていたことなどが分かろう。
石田未得の「吾吟我集」(慶安2年)
◆石かれい石もちなどと重ねつつ みさごの鮓のおもしにやする
「古今夷曲集」(寛文6年1666年)
この時代の俳諧狂歌を見てみると
◆子供をば鮨にするほど持ったれど いひがなければひ干しぞする
◆仏にはまだなまりの魚の鮨 菩薩界までおしかかりたや
◆鮎くての後の心にくらぶれば むかしは鮨もおもはざりけり
◆魚篇に春加ははれる鮨だにも すきなお口に飽かれやはする
◆近江鮒宇治丸鮎の鮨もあれど おされぬ味は鰆なりけり
◆数おほふ江鮒のうろこ福島の 人は仕馴れてよいすずめ鮨
◆青たでもそへてはなさん羽なくて 飛ぶほどうま雀ずしとは
◆秋風のふく島人のをどる(踊)とて すずめ鮨ほどあつまりにけり
大阪福島の名物として「雀ずし」
寛文6年(1666)の『古今夷曲集』
◆数おおふ 江鮒のうろこ 福島の 人は仕馴れて よいすずめ鮨 なる歌で、ほぼ証明される。このすしが、江ブナ(ボラの若魚)のすしであったことも判明する。
「後撰夷曲集」(寛文12年1672)では
◆此魚は都に馴れし鮨ながら 世にうじ丸と人はいふなり
◆口のうちにはおと(羽音)の高くきこゆるは 喉を飛びこす雀鮨かも
◆ちょこちょことおどれ(踊)どへらぬ我腹は飯の過ぎたる雀鮨かも
◆其味もよしや難波の雀ずし 喉のあたりを飛ぶやうにあれ
いえることは一様に馴れずし、ことに生成であって、宇治丸のごときも産地ででは なく消費地で漬けている こと。福島の雀ずしのほか、サワラのすしが特に人気が
あることなどである。
「若えびす」(元禄15年1702)蕉門の俳諧
福島の踊りではないが、祭礼にすしは今日同様に付き物だったと見えて、「若えびす」(元禄15年1702)の付合に
◆ちかうなる まつりの鮓はつきゃったか がある。
蕉門の俳諧付合を見ると 「熱田三歌仙」(貞享3年1684)には
◆清水をすくふ馬柄杓に月 閑水
◆面白き野辺に鮓売る草の上 東籐
◆宿の土産に撫子をほる 士山
「猿簔」(元禄4年1690)では
◆うそつきに自慢いはせて遊ぶらん 野水
◆又も大事の鮓をとり出す 去来
◆堤より田の青やぎていさぎよき 凡兆
「続猿簔」(元禄7年1694)
◆通りのなさに店たつる秋 支考
◆盆じまひ一荷で値ぎる鮨の魚 芭蕉
◆昼寝のくせをなほしかねけり 惟然
「となみ山」(元禄7年1694)
◆点かけてやる相役の文 浪化
◆此の宿をわめいて通る鮎の鮓 浪化
◆青田うねりて夕立のかぜ 芭蕉
季節は夏。漬けておいて時々上から起こして食べているのだ。
芭蕉の弟子のうちにも江戸の其角はよくすしの句をつくっているが、例によって 難解の句が多い。
◆朔日に七里は出たり名古屋鮓
◆石の枕に鮓やありける今の茶屋
◆夕立や傘はやぶれて鮓の蓋
◆明石より神鳴はれて鮓の蓋
◆貫之の鮎の鮓くふわかれ哉
◆飯鮓鱧なつかしき都かな 初句は、
六月朔日に尾州侯献上のアユずしが、「七里の者」(七里ごと江戸まで配置してある飛脚で、御三家、出雲侯などだけに特に許されたもの)の手によって江戸へ運ばれること。
第二句は田舎風景 第三、四句は永代橋で夕立にあったときの作。当時古傘の紙をすし桶の表に目張りに用いた。第五、六句は送別の句である。
井原西鶴の「一代男」(天和2年1682)
滋賀県大津の柴屋町の遊郭を述べて
◆立よる者は馬かた、丸太舟の水主共、浦辺の猟師、相撲取、鮨屋の息子、 小間屋の若者、恋も遠慮もむしゃうやみ・・・・・ と、すし屋をあまり尊敬していない。古い時代のこととて漁夫同様の殺生商売だか都会人に嫌われたのだろう。
笑話集「福禄寿」(宝永5年1708)
和泉流の狂言本は元禄中の出版だが、内容はもっと古い。 その中にすしが二種出てくる。
◆「末ひろがり」 鰻の鮨をばえいやっと頬張ってようか酒を飲めかし。
◆「目近大名」 鱒の鮨を頬 張って諸白(美酒)を飲
寛永19年(1642) の大蔵流伝本ではこうなっている。
◆内へ入ってどぢゃうのすしをほおばって、諸白を呑めやれ
和尚の秘蔵の鮨を小僧がそっと食べてしまって飯粒を本尊の口のまわりに塗りつけておいた「食わん食わん」の話が載っている。饅頭の餡を塗りつけるのとどちらが古いか知らないが、すしの普及と坊主の生臭ぶりとはわかる。
すしの馴れさせる加減のむつかしさを説いている。
「連俳歌仙行」(享保12年1727)
◆明暮に詣であふぐ梅の宮 正珍
◆鮓の加減の一子相伝 蓮ニ
◆咲比と告やる夏の花に来て 光純
竹田出雲の「義経千本桜」(延享4年1742)鮨屋の段
◆春は来ね共花咲かす 娘漬た鮓ならば なれがよかろと買に来る風味も芳野下市に売り弘めたる釣瓶鮓御鮓所の弥左衛門留守の内にも商売に抜目もない(内)儀が早漬に娘お里が片綿襷裙に前垂ほやほやと愛に愛もつ鮎の鮓押さえてしめてなれさする味い盛の振袖が釣瓶鮓とはものらしいとあるのは、演劇的にもさることなが釣瓶ずしが原則として馴れれずし(生成)であり、しかも早漬もあったことを物語っている点に注目したい。●歌舞伎や浄瑠璃にも登場
延享3年(1746)に完成した竹田出雲の『義経千本桜』には、源氏に破れた平維盛をかくまう役どころとして、このすし屋が登場する。
◆あらすじ
吉野山中をさまよっていた維盛は、釣瓶ずしを商うすし屋の弥助に遭遇する。弥助は、かって維盛の父重盛に恩義を受けていた人物で、自ら家に作男として維盛を招き入れ、家族にも内緒で、敵の目を欺くことにした。この時、弥助はその名を維盛に譲り、自名を弥左衛門と改名する。維盛は、いつしか弥左衛門の娘お里と恋仲になり、祝言を上げる運びになるが、その前夜、維盛を案じて吉野を訪ね歩いていた妻子と再会する。すべてを悟ったお里は、父とともに維盛一家の逃亡を手助けする。しかし、お里の兄で名うての厄介ものである権太が維盛の正体を聞きつけ、維盛の身柄を源氏の追っ手に引き渡すと宣言。一足先に家を出た維盛たちの後を追い、やがて「維盛の首を取り、妻子は生け捕りにしてきた」と帰ってきた。居合わせた源氏方の梶原景時、首の入ったすし桶と妻子を引き渡した権太は、褒美をもらうが、逆上した弥左衛門に斬りつけられてしまう。死に際権太が言うには、桶の中の首は、あらかじめ弥左衛門が準備しておいたもの、差し出した妻子は自分の妻子だという。はたして、維盛一家は元気な姿で現れる。権太は改心し、わが身の家族と引き替えに維盛を守ったのだった。その後、首と妻子を連れて行った梶原も、すべてを承知の上で維盛一家を見逃したことも判明。維盛は一人出家するとて、吉野を後にする。土地の人はアユといわず、アイと発音する。さればこそ『義経千本桜』の◆愛に愛もつ鮎の鮓 なる一節が生きてくる。
田沼意次は失意のうちに世を去る
◆白河の清き流れにすみかねて 元の濁りの田沼こいしき
という抵抗精神(?)はついに楽翁を失脚せしめた。
コハダのすし鯛のすしと売り歩いていたが、いずれも数日漬け込んだのばかりだ。
「わすれのこり」(天保13年1758)で茂蔦は
◆「早春のころは、一夜明ければ小はたの鮨うり、玉子うり引きも切らず売り来り しが」 と、このころをなつかしんでいる。
歌麿の「絵本江戸爵」(天明6年1786)にこれに関連した狂歌が2つ載っている。
◆夜や冷えし人にやなれし通り町 ゆき合いの間も鮓や売るらん
◆夕はてにおまんをほめて通り町 つめておしあふ見勢のすし売
越智為久は60余歳になって安永、天明の交を追憶し、当時の流行物の歌を紹介 している。
◆三寸紋五寸模様に日傘こはだの鮓に花が三文
衣服の紋や模様が大きくなったり、だれもかれもが日傘をさすと共に、コハダのす しが流行したことに注目したい。
「青木賊」(天明3年1783)の付合には
◆不埒(ふらち)なり御光の陰に鮓の桶
「風流志道軒伝」(宝暦13年1763)で平賀源内
平賀源内はさらに当時の坊主共の醜態をあ ざけって
◆柔和にんにく葱ざふすい(雑炊)、むき玉子松魚(かつお)の雉焼(きじやき)、 厭離江戸前大かば(蒲)焼、鯵(阿字)本不生の早鮓を、じんばら腹のはる程に取り込み、八功徳水(清酒)のあつかん(熱燗)を引っかけ、雑修自力の心をふり捨て、只一心に心に女郎狂ひと手きびしい。
雑俳では「武蔵川」にすしの句が多い。
◆鮓桶のきのふにけふは投出され (寛延1年1748)
◆一夜鮓宮と桑名の人ごころ (寛延3年1750)
◆一夜鮓妾がつけてもらはれる (宝暦3年1753)
◆唯あれば少しうらみの鮓の蓼 (宝暦7年1761)
◆祝ひ日の気を引立る酢の匂ひ (明和8年1771)
すしの名句は蕪村
なんといってもすしの名句は蕪村にとどめをさす。
「五車反古」(天明3年1783)に
◆胡蘿蔔(にんじん)の花は咲かずもありぬべし 田福
◆下福島の鮓なるる比 蕪村 本領は何といっても発句で
◆馴れ過ぎた鮓をあるじの遺恨哉(宝暦中)
◆鮓桶をこれへと樹下の床几かな(宝暦中)
◆鮓つけて誰待としもなき身哉(明和8年1771)
◆蓼の葉此君と申せ雀鮓(安永6年1771)
◆鮒ずしや彦根の城に雲かかる(安永6年1771)
◆鮓おしてしばし淋しきこころかな(安永6年1771)
◆鮓を圧す我酒醸す隣あり(安永6年1771)
◆鮓をおす石上に詩を題すべく(安永6年1771)
◆すし桶を洗へば浅き遊魚かな(安永6年1771)
◆真しらげのよね一升や鮓のめし(安永6年1771)
◆夢さめてあはやとひらく一夜鮓(安永末)
弐亭三馬は「弐亭日記」(文化8年1811)の中ですし屋のいんさつ引札を書いて
柳ずし五昼夜も漬けやのは土手節がはやったころ、吉原通いを馬でしていた野暮な時代の話で、
現在は山谷舟の三挺だての早漬だといっている。
十返舎一九の「東海道中膝栗毛」に長門鮓
「小吉田」のすし(長門鮓)は弥次喜多の懐中には無理だと考えたのが、近くの蒲原宿の鯵や鯖のすしにしょう・・。
◆すしやのふりうり 鯵のすうし、鯖のすうし
上方で鳥貝のすしが喜ばれたことは、「東海道中膝栗毛」京都の条(文化4年1807)に
◆中には上方に流行る鳥貝の鮨なり・・・・・
◆北八「何だ、コレヤばかの刺身を鮨に付けたのだな」
◆鮨屋「御評判の千倉鮨、鯖か鯖か鳥貝や鳥貝や」
◆北八「アレ弥次さん見なせへ、あの鮨は京で喰ったが とんだ好かった一つ やらかそふ」と、江戸者の口にも合ったことがわかる。
「摂陽奇観」(文政2年1819)に「万安売り御代賑いろは歌教訓鑑」というのを収録しているが、その中に ◆り(利)をすこしとりかい(鳥貝、取)のすし(鮓)さばのすし(鮓)あさくさのり(浅草海苔)もやすしまきずし(巻鮓)とあり、海苔巻、サバずしと並んで鳥貝ずじが大衆的だったことがわかる。
贅沢な深川六軒ぼりの松がすし
化政期の贅沢は大御所様(12代徳川家慶)が先頭だから、下々への普及も速い。
喜多村信節はその「嬉遊笑覧」(文政13年1829)において
◆文化のはじめのころ深川六軒ぼりに松がすし出きて世上すしの風一変し と、江戸前ずしの転換期を19世紀初頭に求めている。 松のすしはそれほど有名な贅沢ずしだったので、川柳、狂歌、狂詩にもしばしば読みこまれている。
◆松カ鮓一分ぺろりと猫がくひ(文政)
◆算盤づくならよしなんし松ケ鮓(文政)
◆荒神様へおみやげの松ケ鮓(天保)
◆本所一番阿他家安宅の鮓 高名当時並ぶべきなし 権家の進物三重の折
玉子は金の如く魚は水晶(天保7年1836)
◆伊豆わさび隠しに入れて人までも 泣かす安宅の丸漬けのすし
古く元禄のころ、江島事件で三宅島に流罪にされた色男生島新五郎の
◆初かつを辛子がなくて涙かな の句は有名だ。
この「松ケすし」と本所「華屋与兵衛」とは天保中、水野越前守の倹約令に引っかかり手錠をくらっている。「与兵衛」も文化5年開業というから、だいたい「松ケすし」と同じころのもの。
◆押しのきく人は松公と与兵衛なり(文政)
両国の與兵衛
「与兵衛」が大正12年の大震災まではマグロのような下司魚を握らなかった。そのマグロが今日常人の口に入りにくい。世の嗜好の変化は恐ろしいものだ。
◆鯛ひらめいつも風味は与兵衛ずし買手は店に待って折詰
◆こみあいて待ちくたびれる与兵衛すし客ももろとも手を握りけり
◆流行の鮓屋町々に在り此頃新たに開く両国の東路次の奥にて名は与兵衛客来り争い座す二間の中
おまんずし
歴史の古いおまんすしも栄えていた。
◆鳥飼も鮓もおまんはわるくなし(鳥飼は有名な菓子屋)
◆餅屋と聞けばおまんは鮓屋也
◆何れの歳か初めて聞く鮓屋の店
連綿数代市中に鳴る 海苔玉子塩梅妙なり 知らぬこれ女房お満の情
口を酸くして呼ぶ、鮨売りの声
洒落本『青桜松之裡』(享和2-1802)には、
口を酸くして呼ぶ、鮨売りの声は、おしつよき客のこごとかと疑うばかり。とあり、夕闇がしだいに迫って来る頃、吉原遊郭内の道々を鮨売りは、「ぞめき客」(登楼する当てはないが、何となく廊内をそぞろ歩きしている男たち)の間を縫うようにして売り歩く。
◆先々の時計となって小商い
◆鯵のすふこはだのすふと賑やかさ
◆けちな鮨コハダの皮に飯を張り
◆妖術といふ身で握る鮨の飯
◆握られて出来て食い付く鮨の飯
◆鮓見世 評判はよしののさくら鯛すしされば買人もおしかけてくる
蜀山人の歌
蜀山人の歌文化14年(1817)に
◆和唐紙にもの書くことは御免酒やこはだの酢に豆腐つみ入れ というのがある。
和紙の唐紙に字を書くことなんか真っ平だ。あれは江戸城のご門の外で供待ちしている人足向きの金魚酒やコハダのすしや豆腐のつみ入れ汁みたいなものだから(全部代用品だ)、といった意味である。
◆坊主だまして還俗させて こはだの鮓でも売らせたい
「毛抜きずし」
『皇都午睡』(嘉永中期<1850ごろ>)の謎かけに
◆骨を抜く道具かと思いきや(毛抜きのように)よう食う
小川顕道(文化11年1814)
◆河豚このしろ我等若年の頃は我家は決して食せざりしもの也・・・・・
このしろは 今世 も士人以上は喰はざれども、魚鮓にして士人も婦人も賞翫(しょうがん)す と呆れている。