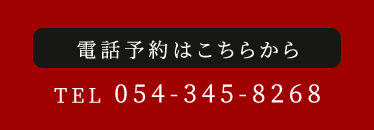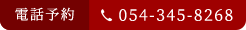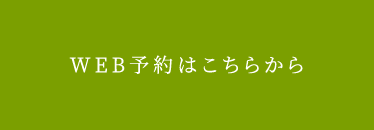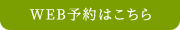瓦版
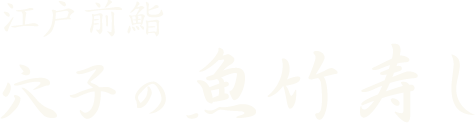 UOTAKE SUSHI
UOTAKE SUSHI
お知らせ
2025年11月26日
NO30「江戸を食す」散し鮨の製法
五目(ごもく)は野菜類の具を飯に混ぜるものであり、
飯の上に具(飯に混ぜる材料を「具」という)とタネを並べるのが散し(ちらし)というのが定義。
タネの並べ方をすし屋間では「吹寄せ」と呼び、
「それぞれのタネが少しずつ重なるように並べるのがコツで、入れ物のどこから見ても
美しいようにしろ」と教えられている。
明治末期のちらしずしの製法
・材料は椎茸、木茸、玉子、おぼろ(芝海老)、小魚、貝類(その季節のもの一種)、
海苔飯、生姜、以上の材料を調えましす。
揉み海苔を鮓飯に混ぜるのは、当時ほとんどのすし店でやっていた仕事だ。
明治中期までは海苔ばかりでなく、しいたけ、かんぴょう、きくらげなども
飯とまぜるすし屋が多かったという。
イメージ